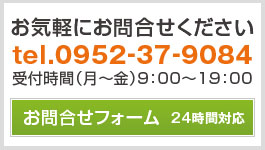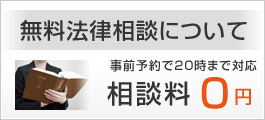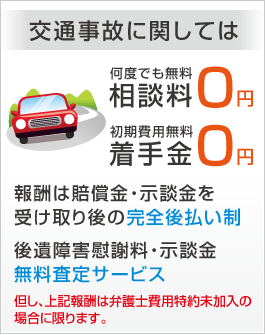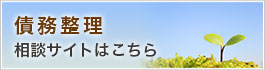Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>4歯喪失の補てつ処置について将来治療費を認めた事例
被害者が本件事故後に施された補てつ処置は、セラミックによるものであるところ、セラミックの強度および周囲歯肉等との親和性に照らして交換が必要であり、1歯につき10万円の費用が必要になること、補てつ物を口腔内で健全に機能させるためには定期的な健診が必要であるところ、その費用は1回5000円であることが認められ、以上の事実関係に、被害者が本件事故により新たに喪失した歯は4歯であること、被害者は症状固定時49歳であったこと(平成22年簡易生命表によると49歳女性の平均余命は38.55年である。)をも併せ考慮すると、本件事故と相当因果関係のある将来治療費は、36万9259円を認めるのが相当である。
(東京地裁平成26年1月27日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>約10年後のインプラント治療費を認めた事例
医師の陳述書によれば、本件事故により脱落した2本の永久歯については、被害者が成人し上顎の成長が止まって安定した頃に、インプラント治療を行うのが相当であると認められる。その時期は、相当因果関係が認められる治療の終了(症状固定)から約10年後と認められる。もっとも、その費用については、2歯で100万円と認定することが相当である。見積書の229万7400円は高めに見積もられている可能性が否めず、約10年の間に費用が低減する可能性も無視できないから、上記程度に控えめに算定すべきである。そして、ライプニッツ方式により中間利息を控除すると(10年のライプニッツ係数0.6139を乗ずる)、61万3900円となる。
(横浜地裁平成25年8月8日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来の左股関節人工骨頭置換手術を認めた事例
被害者は、本件事故により左股関節人工骨頭置換手術を要したところ、人口骨頭の耐用年数は約15年間であり、被害者の事故当時の平均余命が51.52歳であるため、被害者は、将来において3回の同手術を要することとなる。この手術費は、本件事故後の同手術のために要した入院費と認められる65万510円と同額となることが推認される。これをライプニッツ方式により原価計算すると53万5819
円となる。
被害者は人口骨頭の状況確認のために年3回のレントゲンによる画像診断を要し、その診断料の平均は1484.44円であると認められ、これを将来の約95回として原価計算すると5万3526円となる。
(さいたま地裁平成23年11月18日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>インプラント治療費について中間利息を控除して認めた事例
本件事故による八歯欠損の治療方法としては被害者が20歳ころにインプラント治療をするのが相当であると認められる。証拠によると、当初、インプラントの治療費として519万7500円を要する見込みであったが、治療費の値上がりにより、現在では559万6500円を要する見込みとなっていることが認められる。被害者が22歳となった現時点においてもインプラント治療を行っていないので、現時点では治療費として559万6500円を要するものと認められるが、症状固定後の治療費であり、症状固定日から4年を経過しているので、その間の中間利息を控除するのが相当である。年5分の割合による4年のライプニッツ係数は0.82270247であるから、将来治療費は460万4254円である。
(東京地裁平成22年7月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を平均余命まで認めた事例
被害者の症状固定日後の医療関係費は平均して月額5万7000円を下らない。被害者の症状固定日から平均余命までの医療関係費は、以下のとおり、1301万5699円とするのが妥当である。
これに対し、加害者側は、仙台市の公的補助の制度があり、またカルテでは治療費は全額免除との記載があるとして、被害者側の主張する医療関係費をそのまま被害額として認定するべきではない旨主張する。しかしながら、将来の公的給付の受給はあくまでも可能性にとどまり、将来にわたって確定的に受けられるか否かは明らかではない。むしろ、月額5万7000円という額自体も、平成21年2月~同4の医療関係費の平均額(約6万7000円)に照らすと、すでに抑制的な金額であるともいうべきであって、いずれにせよ、加害者側の主張は、上記の認定を左右しない。
(仙台地裁平成21年11月17日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院及びリハビリ費用を認めた事例
被害者は、症状固定後もリハビリステーション病院への入院を続けており、平成19年9月、介護老人施設であるAセンターへ入所し、現在も同所で生活していることが認められる。被害者の後遺障害の状況等に鑑みると、介護なしでの単身生活は困難であり、施設での生活を余儀なくされるものと認められるから、リハビリステーション病院やAセンターでの施設費用は、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。証拠によれば、症状固定日から平成19年4月末日までのリハビリステーション病院の施設費用が286万9887円、平成19年5月より同9の施設費が91万80円(前6月分の平均施設費18万2016円)、症状固定日から平成19年9月末までの日常生活サービス料が37万7370円、Aセンターでの平成19年10月から平成20年4月までの施設費用が35万7602円となる。
(東京地裁平成21年8月26日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来治療費及び入院雑費等を平均余命まで認めた事例
被害者は、自宅介護を強く望んでいるが、被害者の現在の症状に鑑みると、自宅介護とした場合には感染症や合併症等の危険性が増大することは否定できないし、誤嚥等を起こした場合に必要となる迅速的確な処置も病院介護に比べて実現できない危険性が高いから、現段階においては病院介護を選択するのが相当である。被害者の将来治療費は、これまでと同様、月額平均9万円を平均余命まで認めるのが相当である。
被害者の介護については病院介護は相当と認められるから日額1300円で平均余命に相当する入院雑費を認めるべきである。
被害者は本件事故直後から四肢麻痺の状態が続き、今後もその症状は継続することが予想されるから月額9000円で平均余命に相当するオムツ代を認めるべきである。
(大阪地裁平成21年6月30日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来の人工関節手術費用を認めた事例
被害者の、膝関節については、被害者が50歳になるころに変形関節症の治療として、人口(膝)関節置換術を行う必要性を生じる蓋然性を認めることができる。人口膝関節の耐久年数は約20年と考えるのが相当であることおよび被害者の平均余命(約77歳)とを併せて考慮すると、人工関節置換術は被害者が50歳となるころおよび70歳になるころに必要となるものとして、その費用を、症状固定時を基準として、ライプニッツ係数によって現在価値に評価すべきである。
(1)1回当たりの費用15万円
(2)症状固定時の年齢30歳
(3)1回目の手術費用(現在価値)
(4)2回目の手術費用(現在価値)
(大阪地裁平成18年1月19日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後3年間の治療費を認めた事例
被害者は、後遺障害診断書においても、1週間に1度程度のブロック注射が必要との診断もなされていること、被害者は復学し、アルバイト等をしながら、症状固定後も、症状が強いときに、継続して神経ブロックの治療を受けていることが認められ、症状固定後も、一定の期間については、症状が強いときにその緩和のため、神経ブロック等の治療が必要であったと認めるのが相当である。他方で、このような治療も一時的に症状を緩和させるにすぎず、根本的に症状を改善させるものではないこと、胸郭出口症候群の症状については、交通事故による補償問題という心理的負荷等の心因的要因の影響も考えられるところ、同様に神経症状についても心因的な影響があるものと推認されること、ブロック注射のような麻酔治療を長期的に継続することの必要性・相当性等に関する医師の確たる所見も提出されていないことなども総合考慮すると症状固定から約3年後である平成14年8月末日までの治療の限度で、本件事故と相当因果関係のあるものと認めるのが相当である。
(東京地裁平成16年12月21日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>平均余命まで10年ごとに義歯製作費を認めた事例
被害者は、義歯製作費として、将来にわたり、おおむね10年ごとに、少なくとも、110万円(自由診療による製作費である。)の80%に当たる88万円の支出を要する蓋然性が強いものと認められる。加害者側は、保険診療を前提として義歯製作費を算定すべきことを主張するが、保険診療については、補綴に使用する材料を始めとして治療内容に制約があることは公知の事実であり、自由診療により義歯を製作する費用は、事故と相当因果関係のある損害というべきである。そして、被害者は歯科の治療が終了したときは22歳であり、22歳男子の平均余命は55.94年である。したがってライプニッツ方式により中間利息を控除し、被害者の将来の義歯製作費の現価を算出すると127万7056円となる。
(東京地裁平成14年1月15日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。