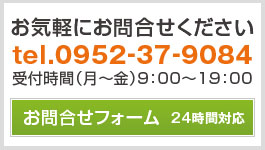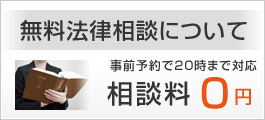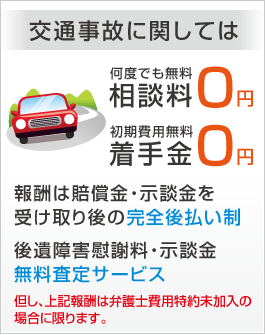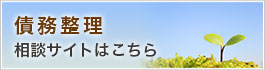Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士・交通事故裁判例>脊髄後索電気刺激法と事故との相当因果関係を認めた事例
被害者は,本件事故後,約7か月間の治療を経ても,自己開眼はするが,追視,従命反応がない状態であったのに,DCS治療開始後の約2か月間で簡易な意思表示が可能になったものであり,被害者の症状の改善が自然経過によるものであるとは考えにくい。DCSの作用機序は必ずしも解明されていないものの,被害者は,DCS療法実施後に改善が見られた症例に多く見られる条件を満たしており,被害者に改善が見られたことからすると,DCS療法が症状に対し,効果があったと認めるのが相当である。以上より,DCS療法は,被害者の症状に対し,一定の効果を及ぼしたものと認められ,被害者の傷害および障害の治療として必要かつ相当なものであったというべきであるから,これらに要した費用についての損害の発生は,本件事故と相当因果関係があるというべきであり,本件事故による治療関係費用としては,合計1198万0812円が認められる。
(大阪地裁平成19年2月21日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>低髄液圧症候群の治療費について事故と因果関係が認められないとしながら,被害者の主張する治療費のほぼ全額を損害と認めた事例
問題は,被害者に低髄液圧症候群,外傷性脊椎髄液漏の傷害が認められるか否かであるが,最も典型的な症状であるところの起立性頭痛は被害者には見られず,ブラッドパッチ療法も見るべき効果はなく,被害者に脊椎髄液漏があるとするにはなお合理的な疑問が残るものと言わなければならない。被害者は,本件事故により,頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)のほか脊椎髄液漏の傷害を負ったとして治療を受けてきたものであるところ,被害者には低髄液圧症候群は認められず,その主張の症状は頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)によるものであると考えるべきであるから,低髄液圧症候群の治療費は,本件事故と相当因果関係が認められない筋合いである。しかしながら,被害者は,自らの症状を訴えて,各医療機関を受診しただけであって,低髄液圧症候群との診断をしてその治療をしたのは医療機関側の判断と責任によるものであるから,被害者が現にその関係の治療費を支払っている以上,それを安易に減額することは相当ではない。
(福岡地裁行橋支部平成17年2月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>事後的には奏功しない結果となった治療について事故との相当因果関係を認めた事例
被害者は,低髄液圧症候群の治療処置として,ブラッドパッチの処置を受けたが,被害者の症状は低髄液圧症候群によるものということはできず,本件事故前からの症状が本件事故によって増幅された面は否定されないものの,専ら本件事故によって生じたものとは客観的に認め難いところである。他方,被害者の本件自覚症状は,これが虚偽であると認めるべき資料はなく,また,本件事故が上記症状に全く関わっていないと認め得る資料もない以上,従前からの軽微な追突事故による症状がさらに本件事故による衝撃によって増悪したものと推認するほかないが,その理由を解明し得る資料はない。そこで,被害者としては,医療機関を頼り,医療機関においても,通常の治療で寛解しない症状につき,試行錯誤しながら,その専門的知見に基づいて先進的な治療方法を選択し,インフォームドコンセントの下に治療を実施するのは自然の流れであって,事後的には,奏功しない結果になったからといって,その治療行為が不必要であったものとして,本件事故と治療行為との因果関係を否定することはできない。被害者は,平成16年5月末日まで加療を受け,治療費258万1840円を要したことが認められる。症状固定は上記期間内のどの時点かであったものと推認し得るが,治療費については,これらが不必要であると被害者に認識し得る時点までは相当因果関係を認めるのが相当である。
(岡山地裁平成17年1月20日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>左坐骨神経損傷の治療を米国で受けた被害者について渡米して治療を受ける必要性を認めることは困難であり,日本における治療費と比較して高額であるとして米国での治療費のうち約50%を損害と認めた事例
米国のS病院での治療等の内容が当時日本で受けられない内容のものであったことを認めるに足りる証拠はなく,かえって,同病院における治療等は,日本においても一般的である温熱療法,牽引,電気刺激,冷湿布および歩行訓練等の理学療法を中心としたものであったことが認められる。そうすると被害者がわざわざ渡米してS病院で治療を受ける必要性があったと認定することは困難である。また,同病院における治療費は,その内容や期間を前提に日本における治療費と比較すると相当に高額である。これらの事情を総合すると,治療費のうち160万円(概ね5割)の限度で本件事故と損等因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成15年5月8日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>診療報酬額について健康保険単価(1点につき10円)の1.5倍(1点につき15円)が事故と相当因果関係のある損害と認めた事例
被害者の父は,事故の翌日病院の求めに応じて被保険者証を提示したが,加害者から,任意保険に入っているから安心して治療してほしいと言われていたので,訴外病院事務員にその旨伝えたのであるから,被保険者証を提示した行為をもって被害者に社会保険による診療を受けさせる意思表示であるとみることはできず,自由診療契約が締結されたと認められる。その後,被害者の父は,入院日に遡及しての社会保険の使用を申し出ているが,訴外病院事務員に遡及しての社会保険使用はできないと言われて,自由診療契約解除の意思表示および社会保険による診療を受ける旨の受益の意思表示をしたことを認めるに足りる証拠はない。
自由診療契約における相当な診療報酬額は,健康保険法の診療報酬体系を一応の基準とし,これに交通事故の特殊性や患者の症状,治療経過等のほか,労災診療算定基準では1点12円とされていること,自由診療の場合,税法上の特別措置の適用が認められていないこと等の諸般の事情を勘案して決定されるべきである。本件の場合は,健康保険の1.5倍をもって相当因果関係のある損害と認めることができる。
(福岡高裁平成8年10月23日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>治療間隔が10か月以上空いた後の治療につき,その間被害者が通常の社会生活を営んでいたと推認できること,体調が良かったこと等より事故との相当因果関係を認めなかった事例
被害者が入通院した事故発生時から平成2年5月1日までの治療・検査はいずれも本件事故と相当因果関係を認めるのが相当であり,被害者固有の心因的要因により不必要,不相当な治療がなされたことを認めるに足りる証拠はない。尚,加害者は,被害者が自ら脳波検査を希望している点をも挙げて,被害者の心因的要因による影響と指摘するが,頭部痛等が長期にわたって継続していることより,被害者が医師に検査を要請するのは理解しえないわけではなく,右希望から直ちに治療ないしは検査が不必要と判断することは出来ない。
他方,平成3年3月12日後の治療については,本件事故とは明らかに因果関係のない胃痛ないし胃障害も診断されていること,A病院の最終診療日(平成2年5月1日)からB病院で再度診察を受ける(平成3年3月12日)まで10か月以上の期間が経過していること,この間,被害者は頭痛等の症状で診察,治療を受けた形跡が認められずカラーを外したうえ継続して仕事を含む通常の社会生活を営んでいたと推認されるこ,平成3年の春には被害者の体調が良かったことに照らすと,本件事故との因果関係は認められない。
(東京地裁平成7年9月6日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>保険会社による医療機関への治療費支払の打切りと,治療費の認定に関して判断した事例
被害者がその客観的原因はともかく,本件事故を契機とする各種の自覚症状のゆえに通院を続けたことは事実というべきであり,この点について被害者に詐病による利得を図る意図があったなどと到底考えることができないから,少なくとも,治療費を本件事故による損害として請求し得ることの可否を論ずる場面においては,被害者の継続的通院をもってそれを責めるのは酷である。
いわゆる一括支払の合意のもとに毎月「自賠責診療報酬明細書」を送付されながら,事実上中途で支払を止めただけで,その後の診療に何らの意義も伝えなかった保険会社はその本来あるべき責務を十分に果たしたとはいい難い。
被害者の治療が必要性・合理性の範囲を超えた期間に及んでいると考えるのであれば,直ちにその旨を伝えるなどして爾後の治療費の支払を拒むことを明らかにすべきであった。
以上のような事情を総合すると,治療費については損害の公平な分担についての信義則上,その全額を本件事故と相当因果関係があるものとして加害者の負担とするのが相当である。
(横浜地裁平成5年8月26日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>自由診療での診療報酬について合意を欠く場合は,健康保険法の診療報酬体系(1点単価10円)が原則であることを判示した事例
現在では,ほとんどの診療報酬が健康保険法の診療報酬体系により算定されているが,当該体系は,診療報酬に利害関係を有する各界の意見および公益を十分に反映させ,その調和を図りつつ公正妥当に定められている。そのなかで,1点単価を10円とし,診療報酬点数表の点数にこれを乗じて診療報酬額を算定する方法は,一般の診療報酬算定の基準として,合理性を有するものである。
自由診療において,診療報酬についての合意を欠く場合であっても,原則として診療報酬体系(1点10円)が診療報酬算定の基準となり,ただこれを修正すべき合理的事情が認められる場合には,その事情を考慮して基準に対し,当該事情に即した修正を加え,相当な診療報酬を決定するのが相当と解すべきである。(本件判決は,自賠責診療単価が,公立病院1点20円,その他神戸・阪神地区の病院1点26円から30円であること,他の患者の場合で1点単価25円で診療報酬の支払いを受けたことがあること,等の各事実を総合して,診療報酬体系を修正すべき合理的事情があると認め,1点単価25円で算定した治療費を被害者の損害として認容した。)
(神戸地裁平成4年3月27日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>自由診療において診療報酬の合意を欠いた場合に,健康保険法の診療報酬体系を基準として診療報酬額を算定した事例
医師の診療行為が必要適切か否かを審査する基準は,診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準に照らし,診療当時の患者の具体的な状況に基づいて客観的に判断して適応を有する病状も存在しないのに,これを存在するとして治療するなど当該治療行為が合理性を欠く診断に基づいてなされたものであるときなど,当該診療行為が医師の有する裁量の範囲を超えたものと認められる場合に限り,必要適切なものとはいえない過剰な診療行為というべきである。
自由診療においても診療報酬額は,社会通念に従った合理的なものであることが必要であり,交通事故においては,一層そのことが要請される。健康保険法の診療報酬体系には,一般の診療報酬を算定する基準としての合理性も存するのであって,自由診療における診療報酬についての合意を欠く場合の診療報酬額についても,健康保険法の診療報酬体系を基準とし,かつ,ほかにこれを修正すべき合理的な事情が認められる場合には,当該事情を考慮し,それらに即応した修正を加えて相当な診療報酬を決定するのが相当である。
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>傷害治療費計算の基礎となった1点単価25円の基準を結果的に肯定した事例
被害者が訴える症状は,事故後,眼科的訴え,胸部圧迫などの不定愁訴が主となったことが認められるが,一般に傷病に対する訴えには個人差があり,いわゆるむち打症については患者自身でないと理解できない不定愁訴があることも顕著な事実であって格別これを過剰であると非難すべき合理的理由はない。
診療医の注射,投薬等,施療方法の相当性についても,一般に医師は,医療の専門家としてその施療方法等について相応の裁量幅を有しているというべきであって,特段の事情もないのに,第三者が当該治療方法を不相当と断ずることは困難である。これを本件についてみても,これを過剰診療と断ずる確証はない。
治療費計算単価は,各府県によって異なるのが実情で,自由診療の場合は,20円の単価が基本だが,他方他府県では30円とする病院も多く存在し,これは突出して高単価であるため,単価25円を採用したものであることが認められる。これらの情況からすると,治療費計算の基礎とした単価25円は,全般的比較としては高いというほかないが,さりとて,これを不当と解することも困難である。
(大阪高裁昭和60年10月29日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。