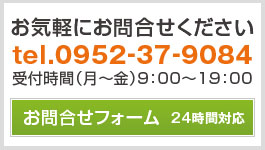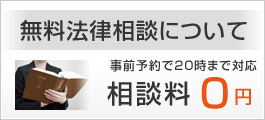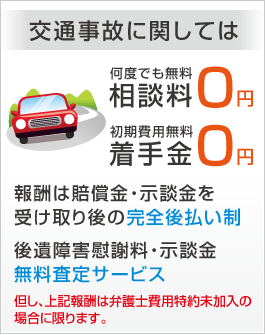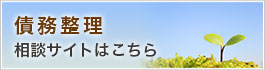Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院雑費を日額1500円で認めた事例
被害者に残存する後遺障害の程度に鑑みれば、被害者には、一生にわたって、従前と同様の入院治療が必要であると認められるから、平均余命16年間につき、日額1500円を前提とする入院雑費が必要となる。症状固定後の介護雑費・入院雑費は、次のとおり、593万3640円が被害者の損害として認められるべきである。
(大阪地裁平成26年4月25日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費を日額1000円で平均余命まで認めた事例
被害者には高次脳機能障害(5級)や複視(10級)の後遺障害が残存しているが、日常生活動作は自立し独りで外出することも可能である。複視に加え、高次脳機能障害による注意障害、感情の易変容、抑鬱などの症状が残存しているため、声かけや見守りを必要とすることはあるが、その程度は、必要に応じ日常生活上の動作や注意を促す程度で足りる。そこで、介護費については日額1000円を認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成26年6月27日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>母親の見守り等の介護費用を認めた事例
被害者は、退院後症状固定までの被害者の状況に照らすと、見守り等の随時介護が必要であったと解される。被害者の生活状況からすれば、平日の日中は施設に通い、月曜から金曜ないし土曜にはヘルパーの訪問を受け、土曜ないし日曜は母親の見守り、兄の指導等を受けていたものといえる。施設への通所、ヘルパーの介助は、実質的に職業付添人による介護と同視できるところ、実際に被害者が出捐した費用(12万1215円)については、実費として損害を認めうる。母親の見守り等については、近親者による介護として捉えられるのが、その介護内容に照らし、日額4000円とするのが相当である。症状固定日までの土曜、日曜、祝日の日数は154日と認められるので、総額は61万6000円(4000円×154)となる。
(大阪地裁平成26年3月20日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を日額4000円で平均余命まで認めた事例
被害者の年齢、後遺障害の内容・程度に、症状固定後の生活状況等に照らし、平均余命について、家族による随時の声掛け、見守り介護の必要があるものと認め、日額4000円を事故と相当因果関係のある障害と認めるのが相当である。被害者は、情報処理速度の低下、計算力の低下等のほか、感情面のコントロールが困難となっていることが認められ、脳挫傷後遺症による高次脳機能障害について3級3号に該当するものした判断は合理性を有する。被害者の社会生活・日常生活の状況を鑑みると、声掛けや介助なしでも日常生活の動作を行うことができる範囲が相当程度認められることを踏まえても、通常の社会生活・日常生活を全うするためには、なお生活の一部分において、家族による随時の声掛けおよび見守り介護の必要があるというべきであるから、そのための介護料の額としては、上記の限度で認めるのが相当である。
(東京地裁平成25年12月25日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料を施設入所月額を基礎に平均余命まで認めた事例
859万9476円
被害者は、特別養護老人ホームに入所し、要介護4の認定を受けており、近々施設を退所しなければならない事情は認められない。被害者を新築物件で介護したいという子の心情は十分に理解できるが、子もその妻もフルタイムで働いており、被害者の心身の状況に照らしても、在宅介護には一定の困難を伴うものと思われる。しかるに、新築物件の建築は進められているものの、子宅は新築物件とは別にあり、具体的な同居の目処は立っていないし、施設入所が長期に及ぶなか、具体的な将来の介護計画を立て、入所施設と連携を取りながら在宅介護に向けた取り組みを行い、実際にも在宅介護の実績を積み上げるといったことが一切行われておらず、新築物件も具体的な被害者の在宅介護状況に沿うように設計されているものではない。在宅介護を可能とする医師等の判断もなく、在宅介護の蓋然性について立証があるとは認めがたい。
⓵ 平成20年8月~平成25年6月(口頭弁論終結時まで)
7万4192円×59月=437万7328円
⓶ その後平均余命まで
7万4192円×12月×5.0757-7万4192円×4月=422万2148円
⓵+⓶=859万9476円
(名古屋地裁平成25年8月9日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>平均余命までの施設費用として年額336万円を認めた事例
平成25年3月には入院先から施設への転居の蓋然性があるものとする。
平成24年11月~平成25年2月
入院費用相当額の限度で認める。
入院費用月額13万800円×4=52万3200円
平成25年3月以降平均余命まで
年額336万円(月額28万円(被害者が入居可能な施設の月額費用(介護保険自己負担分含む)の平均値))×(平均余命までのライプニッツ係数14.0939-症状固定からの7年のライプニッツ係数5.7864)=2791万3200円
別途、入居一時金等(平成25年3月~症状固定後7年に達するまでの月額費用分を含む。)として1500万の限度で本件事故と因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成25年1月30日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を平均余命まで2万円で認めた事例
母親が67歳になるまで,3年間母親が中心になり介護が行われる予定で日額8000円が相当である。
母親67歳以降平均余命まで,42年間,職業付添人による付添が必要で,日額2万円(24時間を2人で担当する前提で,少なくとも1人日額1万円が必要である。)が相当である。
(京都地裁平成24年10月17日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来の看護費用を定期金賠償方式で認めた事例
本件においては,現時点で被害者の余命や介護環境等の将来の状況を的確に予測すること困難であり,将来に著しい変動が生じた場合には変更判決の制度によって対応を図るのが適当であるから,実質的に賠償金を支払うのは保険会社であって履行が確保できることをも考慮に入れると,将来の介護費用は定期金賠償方式によるのが相当であるというべきである。定期金賠償方式による将来の介護費用等は,A病院の治療費(平均20万円程度)等を踏まえ,近親者の付添費用および付添交通費等も考慮し,過失割合も斟酌すると月額25万円とするのが相当である。
(東京地裁平成24年10月11日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士佐賀交通事故>妻が67歳まで将来介護費月額36万円,以降日額1万5000で認めた事例
妻が67歳まで,被害者は,現在,遷延性意識障害の状態からやや改善がみられ,日常生活に関する介助量が若干軽減され,肉体的な負担が軽減された面は認められるものの,かえって常に看視および声掛けが必要になったと認められる。妻が67歳になるまでは,おおむね近親者の介護で足りるが,ある程度は,職業付添人の介護も必要であると認められ,月額36万円を相当と認める。
その後被害者の平均余命まで,職業付添人介護費用として日額2万5000円を相当と認める。
(大阪地裁平成24年7月25日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>職業介護人による施設介護費を日額3万円認めた事例
被害者の在宅介護はまだ始まっていないが,介護住宅の建設と両親の転居も官僚していることからすれば,本件判決後間もない時期から開始されることを前提に将来付添費を算定するのが相当である。もっとも,在宅介護をするのは両親であり,在宅介護は,両親の平均余命からして22年間と認めるのが相当である。それ以降被害者の平均余命までの間は,施設に入所して介護を受けることになると認めるのが相当であるが,その費用については特段の主張,立証はない。
症状固定後2年間は入院介護を前提として日額6300円で,70%の日数を認める。
最初の8年間は家族介護と職業介護を合わせて日額2万5000円,残りの14年間は職業介護を主に日額3万円で認める。
(名古屋地裁平成24年3月16日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。