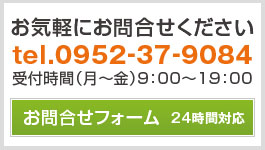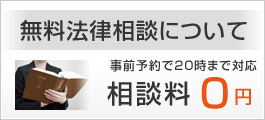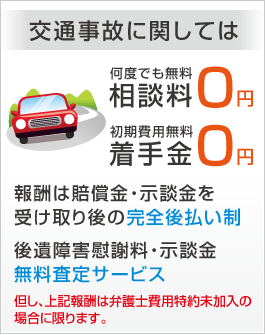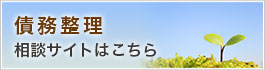Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害につき相当因果関係ある減収分を、役員報酬のほかに労働能力が制限された程度を総合して算定した事例
生活態様:ダンススタジオの経営等をする会社の取締役
算定基礎:¥6,529,560(年額)、¥544,130(月額)
被害者が、本件事故にあわなければ得られるはずであった役員報酬は月額
¥658,180であると認められる。しかし役員報酬は、本来当然に全額
が労務の対価として評価できるとは限らないうえ、被害者が復帰した後の
役員報酬額は¥544,130(年額¥6,529,560)とされている。
そしてH9賃金センサス第1巻第1表企業規模計・産業計・男子労働者の
30歳~34歳の平均賃金が¥5,295,400(顕著な事実)である
ことと対比すると、役員報酬中の労務の対価分としては、せいぜい月額¥
544,130であると認められ、それ以上であると認めるに足らない。
相当因果関係ある減収分については、被害者の会社が恣意的に減額割合を
決定している可能性は否定できないので、被害者が現実に支給された役員
報酬額のほかに、労働能力が制限された程度を総合して本件事故と相当因果
関係のある休業損害を算定するのが相当である。そこで、治療経過を前提に
被害者の労働能力が制限された割合を判断すると、入院中の50日間は
100%、その後H10.1.31~H10.4.30の90日間は平均
して50%の限度で労働能力が制限されたと認められる。
休業日数:入院期間である50日と通院期間である90日の合計140日
認容額 :¥1,699,474
(東京地裁 平成13年1月29日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>作家である被害者が法人成りした有限会社の損害を認定した例
生活態様:被害者は作家で、個人が法人成りした有限会社との間で機関としての代替性
はなく、経済的に一体をなす関係にあるということができる。
算定基礎:年額¥10,338,81(有限会社の事故後の損失額)
認容額 :¥6,513,450
会社の損害は、第1事故および第2事故と相当因果関係がある。
ただし、寄与度減額30%および過失相殺10%を適用
(東京地裁 平成12年3月29日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>被害者の労働を得られない期間も被害者に月額¥1,000,000の役員報酬を支払ってきた会社の報酬支払分を損害と認めた事例
会社の損害:¥8,885,160
被害者は、本件事故当時原告会社の代表取締役であり、従業員は25名ばかり
を擁していたこと、被害者の負傷休業中も原告会社は営業を続けていたこと、
そして原告会社は、被害者の欠勤中も月額¥1,000,000の役員報酬を
支払ってきたことが認められる。被害者本人は、その休業により営業成績が
落ちた旨供述するが、これを裏付ける的確な証拠はない。
原告会社は被害者の労働を得られないことにより、賃金センサスによる平均賃
金程度の被害を被ったと評価するのが相当である。治療状況からみて、被害者
は、当初7か月は全く稼働できず、その後4か月は10%程度、その後7か月
は20%程度しか稼働できなかったと認められる。
認容額:¥8,885,160
(神戸地裁 平成11年4月21日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>専務取締役の休業損害につき、基本給、役職手当の全収入がその労働の対価であることには疑問があるとして、賃金センサスを用いて算定した事例
生活態様:パチンコ店を経営する株式会社の専務取締役
算定基礎:月額¥539,700
(H4賃金センサス企業規模計・学歴計・男子労働者40~44歳平均賃金)
被害者は基本給¥1,000,000、役員手当¥200,000の計
¥1,200,000の月収を得ていたこと、母親はほとんど営業に関わ
っていないが、基本給¥1,000,000を得ていたこと、被害者の基
本給も被害者自身が決定していたことからすると、被害者の全収入が被害
者の労働の対価であることには疑問があり、そのかなりの部分は実質的な
利益配当分であると推認できる。
休業日数:19か月
被害者の負傷内容、症状の推移、就労状況からすると、被害者は事故から
3か月間は就労不能であり、その後3か月は平均してその労働能力の80
%を失い、その後13ヶ月は平均してその労働能力の20%を失っていた
と認められる。
認容額 :¥4,317,600
(大阪地裁 平成9年6月13日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>会社経営者の休業損害につき、業務遂行上の支障の程度は7割であり、給与のうちの労働の対価としての性質を有する部分は5割であるとして算定した事例
生活態様:夫経営の病院の税金対策のための会社を経営
同病院に対する医薬品等の納入や給食、掃除、診療報酬請求等の経理事務が
主たる業務
薬剤師資格を有する被害者がその経営および業務全般を取りしきっていた。
算定基礎:年収¥9,000,000
H3の給与¥18,000,000のうち労働の対価としての性質を有する
部分は5割と認めるのが相当
休業日数:20日
26日間の入院期間のうち休業を余儀なくされたと認めるべき期間は20
日間程度
しかも、その間に生じたと認めるべき業務遂行上の支障の程度は7割と認め
るのが相当
認容額 :¥345,205
(神戸地裁 平成7年2月28日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>建設会社の代表取締役の休業損害について,所得のうち,役員としての稼働の対価分を70%とした事例
生活態様:資本金¥4,000,000の土木工事・建築工事の設計・請負・施行等を
業とする会社の代表取締役
従業員は正社員が約7名,日雇いが約70名
算定基礎:月収¥1,050,000
本件事故前3ヶ月の月収¥1,500,000のうち,稼働の対価分は,
その7割である¥1,050,000と見るのが相当である。
休業日数:41日
被害者が休業したと主張するH4.2.12までのうち,事故から3週間
は労働能力を完全に喪失していたが,その後は現実に通院した日数の2倍
である20日間は労働能力を喪失していたものの,それ以外は稼働が可能
であったと認めるのが相当である。
認容額 :¥1,435,000
(大阪地裁 平成6年5月12日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>会社代表取締役について,個人会社で職務内容も肉体労働が多いことなどを理由として,役員報酬全額を労務提供の対価とした事例
生活態様:建物解体工事・建材卸業等を主たる営業目的とする会社の代表取締役で,
役員報酬として月額¥1,000,000の支給を受けていた。
算定基礎:月額¥1,000,000
会社は被害者の個人会社であり,被害者の職務内容も,受注の際の見積
のほか,ダンプ・重機の運転および土砂・廃材等の積み降ろし等の肉体
作業が多く,右役員報酬はその全額が労務提供の対価と見るべき。
休業日数:3か月間(H2.6.9~H2.8.31)
本件事件との相当因果関係のある就労不能期間はH2.6.9より
H2.8.31までの3か月間である。(被害者主張は6カ月間)
認容額 :¥3,000,000
なお,被害者側の主張する会社の損害については,被害者に実権が集中
していたことは認めるが,事故当時,従業員(8~9名)に対し被害者
が仕事の指示をしていたこと,また被害者の就労不能と相当因果関係の
ある業務受注不能分の代金額ないしはその割合を認定することはできな
いとして不認
(千葉地裁 平成6年2月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>大卒1級建築士の会社代表取締役について,被害者主張の月額給与¥1,000,000は信用し難いとし,賃金センサス大卒男子30~34歳平均給与額を基礎とした事例
生活態様:大学の建築学科を卒業後,宅地建物取引主任者,1級建築士等の資格を取得
し,S60年に建築の設計,監理および土地の売買とその仲介を業とする
会社を設立し,事業を営んでいた。
算定基礎:年収¥4,677,700
(S60賃金センサス企業規模計大卒男子30~34歳平均給与額)
被害者主張の月額給与¥1,000,000について,決算報告書,源泉
徴収票に記載はあるものの,被害者のいわゆる1人会社であること,
S62.6~63.5の決算期に¥44,000,000余の欠損を出し
たと税務申告をしていることに照らすと,被害者の主張は容易に信用し難い
として採用せず。
休業日数:S63.9.30~H1.6.30は274日間休業
H1.7.1~H2.3.26は241日間労働能力が半減
認容額 :¥5,055,759
(大阪地裁 平成5年5月31日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>代表取締役の就労制限期間中も給与を支払っていた会社は、就労制限部分に対応する限度で損害賠償請求権を代位取得するとした事例
生活態様:資本金¥12,000,000の、土地および中古住宅の売買の仲介、建物
の賃貸を業とする会社の代表取締役で、主な仕事は土地の調査、買収交渉、
官庁等との協議、事務所内での書類決済であったもの
算定基礎:年収¥8,160,000
会社規模、被害者の業務内容、また給料が事故後のS59.4に
¥12,000,000に昇給していること等から、S58の年収
¥12,000,000のうち取締役報酬分を除いた8割程度が労働の対価
たる性質をもつ賃金分である。
休業日数:S58.11.5~11.30は100%、
S58.12.1~S59.4.30まで
は60%、S59.5.1~7.31までは20%の就労制限があったもの
認容額 :¥3,037,333
就労制限期間中も給料を支払っていた会社は、民法422条または同法
702条の類推適用により、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を就労
制限部分に対応する限度で代位取得すると解するのが相当である。
(大阪地裁 昭和62年6月23日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>併合12級女子の休業損害について賃金センサス女性・学歴計平均賃金をもとに認めた事例
生活態様:夫および長男と同居し、家事全般を担当とするとともに事務の仕事をパートタイマーとして1日6時間、週5日就労していた。
算定基礎:年額¥3,459,400(平成22年賃金センサス女性・産業計・企業計・学歴計平均賃金)
休業日数:505.4日
被害者の労働能力喪失率は平成23年3月末までの307日間は100%、平成23年11月末までの244日間は60%、平成24年8月16日までの
260日間は20%と認めるのが相当である。
認容額: ¥4,790,084
(名古屋地裁 平成27年6月26日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。