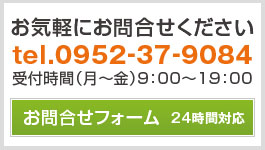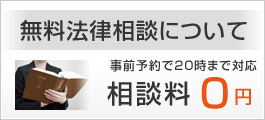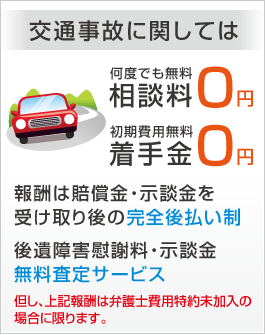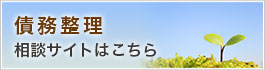Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>事故による欠勤がなければ,会社のモデル賃金に従い昇給するはずであったものとして損害を認めた事例
生活態様:S46.3高校卒業,S46.4に18歳で被害者会社へ入社
算定基礎:被害者会社よりの実支給額および被害者会社のモデル賃金
休業日数:298日間
認容額:¥893,759
⑴超過勤務手当および皆勤手当の減給分
¥131,240
⑵S48~S51年度の昇給差額(事故による欠勤がなければ昇給
により支給されたであろうモデル賃金と実支給額の差額)
¥461,026
⑶昇給遅延によるS52年度以降の損害
¥301,493
(東京地裁 昭和54年11月27日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>52歳男子代表取締役の休業損害について役員報酬月額¥2,800,000の70%を基礎収入として認めた事例
生活態様:株式会社の代表およびスポーツ事業部の中心として,メール
等による業務指示,決済,銀行関係者との面談等を行ってい
た。
算定基礎:日額¥64,438
被害者の役員報酬の中には,単に業績との連動性があるとい
うよりも,むしろ被害者が提供する労務の質量と直接結びつ
いていない部分が一定割合含まれているものと考えざるを得
ず,諸事情を総合的に考慮し,その収入の70%に限り,基
礎収入として認めるのが相当。
休業日数:177日の25%
⑴被害者の休業期間中相当程度の労働能力回復はあったと考
えられること,⑵被害者の業務は決済業務が中心であること,
⑶H23.3.27の段階でソフトボール大会に出席し,相
当程度腰部に負担のかかる活動をすることができたと考えら
れること等の諸事情を考慮し,その25%について本件事故
と相当因果関係のある損害と認める。
認容額:¥2,851,382
(大阪地裁 平成26年9月9日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>48歳男子代表取締役の休業損害について,月額報酬の減少額全額を認めた事例
生活態様:約30年にわたり個人で建設業を営んでいたが,H18.6.8に
株式会社を設立し,代表取締役に就任した。会社の設立以降,従業
員を雇用せず,一人で従前と同様に現場作業を営む内装業務,監督
業務を行っていた。会社設立の際,自らの報酬を¥400,000
と定めたが,H19.7以降,¥200,000に変更。
算定基礎:月額¥400,000
事故前の収入は月額¥400,000であり,労務の対価であると
認められる
休業日数:42カ月
H19.6までは¥400,000の支給を受けているから休業に
よる損害があったとは認められない。他方,H22.12.22ま
で継続的に入院または通院治療を受けており,本件事故による傷害
およびその治療のための入通院により業務を休む必要があったこと,
H19.7以降の支給額が1月あたり¥200,000減少したこ
とが認められる。
認容額:¥8,400,000
(東京地裁 平成26年4月23日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>症状固定時65歳男子会社役員の休業損害を役員報酬¥12,000,000のうち¥9,600,000を基に認めた事例
生活態様:取締役の地位にあり,関連会社においても経理・財務・総務・人事に
関する業務を行っていた。
算定基礎:年額¥9,600,000
本件事故当時,役員報酬として年¥12,000,000の収入を得て
いたが,復職後は,事故前よりも30%少ない業務にもかかわらず同じ
水準の収入を得ている事実に照らすと,その一部は,被害者の労働の内
容や程度とかかわりなく得られていたと推認するのが相当。被害者の従
前の職務の内容に鑑みれば,役員報酬のうち,労働との対価的関連性を
有する部分の金額は,一般的な労働者が得るであろう平均的な賃金の2
倍程度の額に相当する¥9,600,000と認めるのが相当。
休業日数:15カ月
認容額:¥12,000,000
(東京地裁 平成25年3月13日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>事故時59歳男子代表取締役の休業損害について症状固定日までの4年5カ月について70%の就労制限率で認めた事例
生活態様:建築部門と健康食品部門のあるA社の代表取締役であるが,
建築部門の現場作業には被害者しか従事していなかった。
算定基礎:年額¥6,720,000
A社におけるH14年度に得ていた報酬額の80%
休業日数:53月×70%
H18.12.18初診時の症状について医師が就労は厳しいと
証言していること,症状固定日(H19.12.11)時点にお
いても,頭位変換時平衡感覚異常を残していて,本格的には稼働
していなかったこと等の事実を総合考慮して,症状固定日までの
約4年5カ月間(53月)についての就労制限率は,平均して
70%と認めるのが相当。
認容額:¥20,776,000
(大阪高裁 平成23年7月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業損害として¥2,500,000を認めた事例
会社の休業損害:¥2,500,000
会社は,技術者は被害者1名,従業員は2名であり,航空測量
は技術者がいなければできず,会社の営業も成り立たないとこ
ろ,会社は,H11ないしH13にかけての第10ないし12
期の売上高は¥20,000,000前後あったものの,H
14.9.10からH16.3.1までの売上が半分以下に落
ち込んでおりこれらの事情を総合すると,本件事故による被害
者の傷害と会社との損害との間には相当因果関係が推認される。
前期のとおり会社の売上の減少があり,本件事故によるもので
あること,しかし,会社は本件事故前の12期は赤字であった
こと,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を総合すると,会
社の休業損害は¥2,500,000と認めるのが相当である。
会社は12期は赤字であったが,営業活動をしており,被害者
らおよび従業員に報酬等を支払っていたものであるから,単に
赤字であるからといって直ちに損害が発生しないということは
できない。また,被害者と会社は別人格であり,被害者への支
払分を会社の損害の支払にあてることはできない。
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>会社代表取締役の休業損害について賃金センサス男性労働者全年齢平均賃金で認めた事例
生活態様:建設業を営む会社の代表取締役
算定基礎:年額¥5,659,100(H13賃金センサス男性労働者全年齢
平均賃金)
被害者の役員報酬は,H12分が¥4,063,735,H13分が
¥8,317,000であることが認められるが,被害者の役員報酬
が会社の売り上げに応じて決定されていたことが認められるうえ,
H12分とH13分の各役員報酬額に倍以上の開きがあることからす
れば,景気等の影響による会社の売上高の変動によって,被害者の役
員報酬額が大きく変動する可能性があることを否定できないから,
2年分のみの役員報酬の平均額をもって基礎収入とすることはできない。
休業日数:178.7日
入院期間中の35日間は100%の就労制限を受けたものの,退院し
た翌日であるH13.4.7からH14.7.29までの1年と114
日間においては平均30%の就労制限を受けたにとどまるというべき
である。
認容額:¥2,770,632
(東京地裁 平成18年7月18日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>赤字の土木会社経営につき、事故前の収入全てを基礎収入として認めた事例
生活態様:被害者は土木会社を経営し、被害者とその妻が経営者であった。常雇いの従
業員は2名で、必要に応じて臨時雇い、被害者および妻も現場に出て作業を
担当していた。
算定基礎:年額¥4,400,000
被害者は土木会社のH12の年間売上げ¥61,490,000、被害者の
報酬¥6,000,000、妻の報酬¥3600,000、H13の年間売
上げ¥54,310,000、被害者の報酬¥6,000,000、妻の報
酬¥3,600,000、H14の年間売上げ¥24,140,000、原
告の報酬¥4,400,000、妻の報酬¥1,600,000であった。
原告の報酬はその大部分が労働の対価として見て良く、H14の売上げがH
13に比べて大幅に減少していることを考慮してH14の被害者の報酬額
440万円を基礎年収とするのが相当である。
加害者は、事故直前は被害者の会社は赤字であったから、収入がなかったと
主張したが、裁判所は、被害者夫妻が自己の財産をつぎ込んで会社の存続を
はかるか、会社に見切りをつけて廃業するかは、その相応の報酬を受領する
こととは切り離して考えるべきとして、その主張を排斥した。
休業日数:429日
事故時から症状固定まで429日間、体調不良のため労務に従事できなかっ
た。被害者は会社を解散せざるを得なかったものであるところ、事故時69
歳と比較的高齢であることを考慮すると、通院期間全部について休業するの
もやむを得なかった。
認容額 :¥5,171,506
(名古屋地裁 平成17年7月15日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>女性会社役員の休業損害について役員報酬の3分の1を労働の対価部分として算定した事例
休業損害:¥34,500,000
被害者は事故当時、有限会社P、株式会社Fの役員として勤務し、Fの3店舗
について、仕入の手配、請求書の処理、支払手続、経理等の事務手続き一切を
1人で行い、さらい繁忙期には店舗に出て手伝いをするなどしていた。被害者
の本件事故前のH10の収入は、役員報酬として¥34,800,000であ
ったが、本件事故後は、H11が¥17,400,000、H12が
¥26,100,000、H13が¥26,400,000で、H11から
H13の3年間にかけて合計¥34,500,000、平均すると3分の1の
減収になったと認められる。被害者の前期就労実態ならびに被害者の精神科へ
の入院後は、他の従業員2名を雇用して被害者の行っていた業務を代行させる
などしたことからすれば、すくなくとも被害者に支払われていた役員報酬のう
ちの3分の1程度は労働の対価部分であると認められ、さらに減収となった部
分については被害者が就労できなかったことから減額されたと認められる。
これによれば、被害者のH11からH13の3年間の減収分合計¥34,
500,000は、同人の休業損害と認めるのが相当である。
(名古屋地裁 平成16年5月26日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護時交通事故裁判例>建設機械修理販売業を営む会社代表者の休業損害を賃金センサス男子労働者平均賃金をもとにし算定した事例
生活態様:被害者は、建設機械の修理販売を行う会社の代表取締役で、同社の従業員は
本件事故当時8名であった。同社はK株式会社から専属的に外注を請ける
下請け会社で、K株式会社は、実働の仕事がなくとも、1日8時間、時間給
¥3,250~¥3,300の給与保証をしている。被害者の仕事の内容は
ほかの従業員と同じ重機類の整備である。被害者はH11.5.18~
H12.1.24現場における就労ができなかったにもかかわらず、会社
から本件事故の前後を通じ、年間¥10,800,000の給与の支払いを
受けている。
算定基礎:年額¥7,145,900
H11賃金センサス産業計・企業規模計・男子労働者・学歴計・50~
54歳の年額
休業日数:252日(H11.5.18~H12.1.24)
認容額 :¥4,933,607
被害者と会社を経済的に同一体として被害者が就労できなかったことによ
って会社がK株式会社より受けられなかった請負代金の金額を、被害者の
休業損害とするが、この金額が根拠上明らかでないということで上記の算定
となったもの
(岡山地裁 平成15年6月13日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。