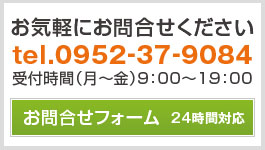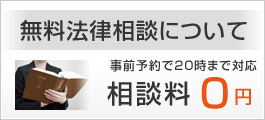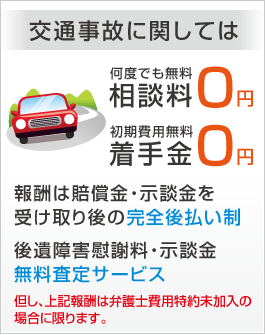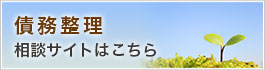Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の21歳男子の将来の介護費用について母親が70歳になるまでは日額8000円,その後平均余命までは日額1万5000円で認めた事例
被害者は,本件事故による後遺障害のために,日常生活における介護を必要とするところ,その後遺障害の内容程度,必要な介護の内容,程度を総合的に勘案すると,被害者の介護に要する費用は,家族による介護については1日当たり8000円,職業介護人による介護については1日当たり1万5000円と認めるのが相当である。
(さいたま地裁平成17年6月17日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の症状固定時33歳男子の介護費用について平均余命46年間にわたり日額1万5000円で認めた事例
被害者の症状の内容および重さからすれば,呼吸管理も含めた介護が生涯にわたって必要であること,被害者は症状固定時33歳であり,平均余命が46歳であること,被害者は本件事故後に婚姻したが,若い妻にとって後遺障害を抱える同人との生活および日々の介護は心身ともに多大な負担を強いられること等が認められる。これらの諸事実からすると,被害者の近親者が中心となって介護を行い続けることは困難であり,介護費用を算定するにあたっては,職業介護者を依頼することを原則とし,近親者が可能な範囲でその補助をすることを前提とするのが相当である。介護の負担は,損害として認められる電動車いす,自宅改造,多数の機器類により,相当軽減されると考えられる。上記事情に加え,被害者において現在まで職業介護人の代金も全て自己負担がないと認められることおよび将来の付添費について本件では生活費控除を行わないことに鑑みると,付添費としては日額1万5000円と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成17年5月17日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の42歳男子の将来の介護料につき,妻が67歳になるまでは日額1万5000円,それ以降は日額2万0800円で平均余命まで認めた事例
症状固定後妻が67歳になるまでの24年間
主たる近親介護者の分9000円のほかに,補助的介護者の分として職業的介護費用を前提に日額6000円を請求するのは相当である。
それ以降,被害者の平均余命まで
主たる介護者は職業的付添人を付するのが相当であり,妻の介護状況に照らせば1日当たり15時間を認めるのが相当である。現時点における単価としては3時間半以上で既に2万円以上を要するというものであるが,将来においては介護市場の拡大および20年余りも将来の問題であることも総合考慮して,本件事故と相当因果関係のある介護費用単価は,上記の80%に相当する日額1万6000円を基礎とするのが相当である。また,補助介護者の現時点における介護費用単価としては,日額6000円を認めるのが相当であるが,将来における介護単価の見通しはいまだ不確定な要素が多々あることを考慮すると,上記の80%に相当する日額4800円を基礎とするのが相当である。
(大阪地裁平成17年3月25日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の34歳男子の付添費について症状固定後母親が67歳になるまでは日額1万2000円,その後被害者の平均余命期間までは日額2万円で認めた事例
症状固定後母親が67歳になるまでの7年間
被害者は,運動機能障害,外傷性てんかん,高次脳機能障害等の状態であり,また,証拠によれば,被害者は,食事,トイレ,移動,入浴等の世話をはじめとして,常時介護が必要な状態であり,母親のみならず,2人の妹や一部は職業介護人に頼らざるを得ないことが認められる。そこでケアサービスの料金表等も参考にして考えると,近親者介護及び一部職業介護を含めた介護費は,1日当たり1万2000円が相当と認める。
それ以降38年間
被害者の症状に照らして,母親の介護が期待できないと考えられる場合の職業介護費としては,上記ケアサービスの料金表等も参考にして,1日当たり2万円が相当と認める。
(東京地裁平成16年12月21日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の23歳女子の将来の付添看護費について日額1万3000円で定期金賠償で認定した事例
症状固定日以後,口頭弁論終結の日まで,現実に職業付添人による付添介護がされたことについて全く主張がなく,そのことを窺わせる証拠もないので症状固定日の翌日から口頭弁論終結の日までの592日間は,それ以前と同様,1日6500円を認めることができる。
被害者は口頭弁論終結時において25歳であり,平均余命によれば,今後58年の生存が期待できる。この58年にわたって,母による近親者看護が期待できないのは自明であり,現に職業付添人による付添がなされていない事実を考慮しても,口頭弁論終結時以降の将来の付添看護費の額は1日当たり1万3000円と認めるのが相当である。
被害者は,将来の貸しおむつ代,将来の室料差額等とともに定期金賠償の方式による賠償を主位的に求めており,定期金賠償の方式による賠償が命じられた。
(神戸地裁平成16年12月20日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>併合4級(高次脳機能障害)の18歳男子の将来付添費について日額2000円で認めた事例
被害者に対する介護の内容は,随時の看視・声掛けであり,常時被害者がそれらを必要とするとはいえない。そして,被害者がかかる介護を要する場合は限られ,毎日,継続的に介護が必要であるとは認められない。被害者には,その生活環境によっては,職業介護が必要になることがないとはいえないとしても,その介護内容や頻度に見合う,本件事故と相当因果関係のある将来の介護料は,平均すれば,1日当たり2000円とみるのが相当である。そして,介護が必要な期間は,症状固定時の平均余命である60年とみるべきである。
(東京地裁平成16年9月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>併合1級の18歳男子の介護費用について随時介護を要するものとして平均余命59年間にわたり日額6000円で認めた事例
被害者の症状に照らして判断すると,精神疾患として後遺障害等級3級3号の認定を受けており,その余の後遺障害と併せても,随時介護を要する程度のものというべきであり,将来の介護費用としては,症状固定後の全期間を通して日額6000円と認めるのが相当である。
(東京地裁平成16年7月13日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の27歳男子の将来の介護費用について,母親による介護が可能な期間は日額8000円,家族介護と職業介護を併用する期間は日額1万5000円,職業介護のみの期間は日額2万円で認めた事例
母親による介護が可能な期間
家族介護費として,被害者の症状が重いことを考慮し,日額8000円をもって相当とする。
家族介護と職業介護を併用する期間
母親が働きに出るため平日の昼間については職業介護人に頼らざるを得ないこと,平日の夜間および週末と祝日については家族介護となること等を考慮して,平均して日額1万5000円をもって相当とする。
職業介護のみの期間
平成22年8月3日から被害者の平均余命の残期間40年間については,平均して日額2万円をもって相当と解する。
(東京地裁平成16年6月29日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の1歳女子の付添費について6歳までは日額8000円,その後母親が67歳になるまでの間は平日は日額1万2000円,公休日は日額8000円,その後の平均余命期間までは日額1万2000円を認めた事例
平成17年から母親が67歳になる年(平成53年)まで
両親が就労することを前提に1年間のうち平日240日について職業介護人による介護がなされ,公休日125日について両親による介護がなされるものと認める。
平成53年から被害者の平均余命期間(平成95年まで)
母親が67歳に達するころには両親によって介護することが困難になるので,全日職業介護が必要になると認める。
(さいたま地裁平成16年4月23日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級3号の57歳男子の将来の介護料について,妻が67歳になるまでの12年は日額8500円で,その後の12年は日額1万8000円で認定した事例
57歳男性の平均余命は24.18年であるから,被害者が自宅で付添介護を要する状態は,医療機関を退院した平成14年2月以降24年間は係属するものと推認される。また,当面の付添介護は,妻によることが期待されるものの,その年齢に照らし,遅くとも妻が67歳に達する平成25年以降は,職業付添人による介護を要する状態となる蓋然性が高いといえる。その他,被害者の要介護度に照らすと,将来の付添費の1日当たりの単価としては,平成25年までの12年間は8500円,それ以降平成37年までの12年間は1万8000円を認めるのが相当である。なお,これは,被害者ら主張のヘルパーの必要性や職業付添人と近親者付添人のいずれも介護する状況があり得ることなど一切の事情を考慮した上での金額であり,別個にヘルパー代を損害として計上することはしない。
(東京地裁平成16年3月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。