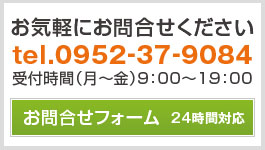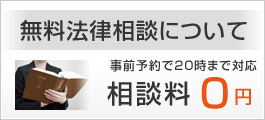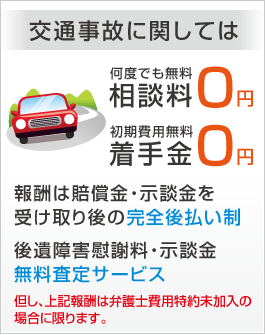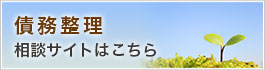Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を書類提出日から30日後とした事例
遅延損害金:(無保険者傷害保険金の請求を受けて加害者とともに被告となっている保険会社側に対して)
無保険車傷害保険の保険金の支払対象額は,賠償義務者が法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額であることからすれば,被害者側の保険会社に対する請求について認められる年5%の割合とすべきであり,これに対する被害者側の主張は採用できない。
被害者側が,保険会社に無保険車傷害保険金の請求に必要な書類を全て提出した平成15年1月31日から30日後の同年3月1日が履行期となるが,同日が土曜日のために履行期は同年3月3日となり,その結果同年3月4あ履行遅滞の起算日となるとした。
※被害者側は,保険金請求の必要書類について,「自動車保険契約内容に関する回答」の内容は保険会社側は知悉していたから必要書類に含まれないかまたは既に提出されていると主張し,他の必要書類の提出日を前提に遅延損害金を請求したが,前記回答は保険約款にて書面で行うこととされていることから被害者側の主張は通らなかった。
(名古屋地裁平成16年9月8日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金は請求を受けた時点から発生するとした事例
国は,自賠法72条1項の保障金請求権は同条項によって創設された公的請求権というべきであるから,この性質にかんがみれば,遅延損害金に関する規定がないのは,もともと遅延損害金を付すことが予定されていないからというべきであると主張している。しかし,国に対する保障金請求権は公法上は民法の支払期日および遅延損害金に関する規定が適用されないと解するのは相当ではない。むしろ,国を当事者とする金銭債権について,会計法が,30~32条の規定において,時効について民法の特則を定めながら,他の事項について触れるところがないのは,公法上の金銭債権であっても,時効以外の点については,その金銭債権の性質がこれを許さないと解される場合でない限り,原則として民法の規定を準用する法意に出たものと解するのが相当である。そして,自賠法72条の定めるてん補金支払い義務について,自賠法および関係法廷は存在しないから,自賠法72条に基づく国のてん補金支払義務は,私法上の金銭債権に準じ,その支払期日について別段の規定が存在しない以上期限の定めがない債務として成立し,民法412条3項により請求を受けたときから遅滞に陥り,同法419条により,遅延損害金が発生するものと解するのが相当である。
(大阪高裁平成15年9月30日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金をまず遅延損害金に充当するとした事例
自動車損害賠償保障法16条1項の被害者の直接請求権は,被害者保護の見地から,認められたものであり,被害者に対し,保険会社に対する保険金額の限度内での損害賠償額の支払請求権を認めたものであり,自賠責保険金の支払は,被害者に対する関係では加害者の損害賠償債務の支払と同視されるものであるから,その充当関係についても民法491条に従うべきである。よって,自賠責保険金支払日までの損害全体に対する遅延損害金にまず充当され,残額が損害元本に充当されるものと解する。
(大阪地裁平成13年11月28日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の請求が制限される理由はないとした事例
不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,何らの催告を要することなく,遅延に陥るものであって,後に自賠法に基づく保険金の支払によって元本債務に相当する損害が塡補されたとしても,右塡補にかかる損害金の支払債務に対する損害発生日である事故の日から右支払日までの遅延損害金は既に発生しているのであるから,右遅延損害金の請求が制限される理由はない。
したがって,本件においては,自賠法に基づき支払われた保険金に相当する損害額に対する本件事故の発生日から右保険金の支払日までの遅延損害金請求は容認されるべきであって,これを棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。そうすると,上告人らの請求は,原審が認容したところに加えて,右保険金に相当する損害額に対する本件事故の発生日である平成8年5月25日から右支払日である平成9年2月14日までの民法所定の年5分の割合による遅延損害金84万7392円の支払を求める限度で容認し,その余は棄却すべきである。
(最高裁・平成11年10月26日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を不法行為時とした事例
弁護士費用に関する損害は,ほかの費目の損害と同様1個の損害賠償債務の一部を構成するから,不法行為時に発生し,かつ,遅滞に陥るが,その額は被害者が被害者が事故時かわ支払時までの中間利息を不当に利得することのないように算定すべきであるとしたうえ,弁護士費用につき,事故後である訴状送達翌日から遅延損害金の支払義務を負うとした原審の判断を是認。
(最高裁・昭和58年9月6日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>損害賠償債務について遅滞に陥るとした事例
本件は,被害者側が加害者側の不法行為により被った損害の賠償責任の履行およびこの債務の履行遅滞による損害金として昭和31年1月22年以降年5分の割合による金員の支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。
そして,右訴訟債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥るものと解するのが相当である。
(最高裁・昭和37年9月4日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>控除した残額の約10%を弁護士費用と認めた事例
被害者側は自賠責保険の被害者請求をしていないが,それをするかどうかは被害者側の自由であり,また死亡保険金3000万円の満額が支払われるとは限らないから,加害者側が主張するように上記3000万円を控除して弁護士費用を算定するのは相当ではない。もっとも,最判昭和44年2月27日判決(民集23.2.441)も判示しているとおり,相当因果関係が認められる弁護士費用の額は,事案の難易,請求額,認容額その他諸般の事情を考慮して定められるべきであって被害者側の主張するように当然に認容額の約1割とすべきものでもない。本件においては特に認容額を増額すべき事情が明らかになったわけではない。そして本件においては,少なくとも遺族固有の慰謝料の合計額750万円については「赤い本」等にも記載されている自賠責保険金の支払基準によれば,極めて容易に支払われたはずである。したがって,弁護士費用の総額は,認容額の総額4894万2275円から上記750万円を控除した4144万2275円の約10%として,410万円とするのが相当である。
(横浜地裁平成25年2月14日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用相当額の損害の発生を認めるとした事例
本件事案の内容,審理経過,認容額(97万1021円)その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は10万円とするのが相当である。なお,仮に,被害者が自動車保険契約の弁護士特約を利用していたとしても,弁護士費用相当額の保険金は被害者の負担した保険料の対価として支払われたものであるから,被害者に弁護費用相当額の損害が発生していないとはいえない。
(東京地裁平成24年1月27日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用について加害者側の主張を認めなかった事例
弁護士費用:720万円
本件の被害者の認容額が7170万784円であるところ,同認容額,本件事故後の経緯等本件に現れた諸般の事情に照らせば,弁護士費用は,被害者が自賠責共済の被害者請求により自賠責共済金を受領しなかったから損害が拡大したとして,弁護士費用の算定基礎としては,これによる額を差し引くべきである旨主張する。しかしながら,被害者請求の制度は,被害者の救済のために設けられた制度であるところ,被害者が原告として訴訟を提起する前には,あらかじめ被害者請求をして自賠責保険金ないし共済金を受領しなければならず,これをしなかったことについて,責められるべき点があるとまではいえない。また,本件全証拠によっても,被害者について,特に責められるべき事情を認めることはできない。したがって,加害者側の上記主張は採用できない。
(大阪地裁平成23年3月11日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>請求額に入っていない弁護士費用を認めた事例
弁護士費用:530万7500円
認容額および本件訴訟の経緯等からすれば,弁護士費用分の損害賠償額としては,両親について各263万円,祖母について4万7500円を認めるのが相当である。なお,被害者らは,訴状において,請求原因の損害の項目としては弁護士費用1300万円の主張をしているが,それを含まない額の請求しかしていない。しかし,弁護士費用を含む認容額としても,被害者側のいずれについても一部認容となり,その請求額を超える認容額にはなっていないし,請求原因としては弁護士費用の損害を挙げていることから,訴状の上記のような記載にかかわらず,上記のとおり弁護士費用分の損害額を含めた認容判決をすべきである(処分権主義にも弁論主義にも反しない)と解される。
(名古屋地裁平成22年6月4日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。