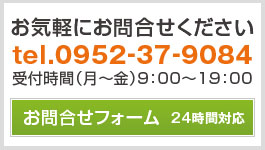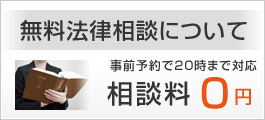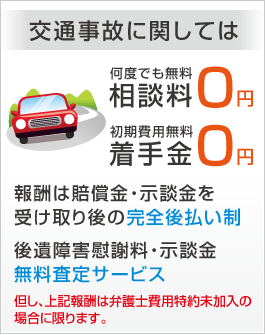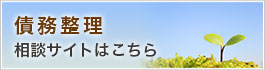Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>被害者の将来の付添費等を定期金賠償で認定した事例
定期金賠償の方式による請求の当否について
交通事故によって受傷した者の損害は,事故発生の時にそのすべてが発生すると観念すべきものではあるが,重度後遺障害者に生ずる将来の付添費,将来の貸しおむつ代,将来の室料差額等の損害は,受賞者の死亡によって発生を止めるのであるから,その数額を一時金の方式で算定するためには,受傷者の余命年数を認定することが必須となるが,重度後遺障害者の余命認定は不可能ではないにしても極めて困難である。上記のような事情の下では,将来の付添費,将来の貸しおむつ代,将来の室料差額等の損害について定額金賠償の方式による賠償を命ずるのには十分な理由があるというべきであり,賠償を請求する者の側でこれを求めるときは,特段の事情がない限り,これを認めるのが相当である。本件において,加害者側は,⓵本件が過失相殺事案であること,⓶今後の賠償義務者の負担,⓷将来の事業変更があった場合の負担,等の事実を挙げて,定期金賠償は認められるべきではないと主張したが,いずれも定期金賠償を不相当とする理由になるとは認められない。よって,被害者が主張する上記損害費目については,定期金賠償による損害を認めるのが相当である。
(神戸地裁平成16年12月20日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>飼育依頼代金について業務上の損害と認めた事例
被害者は,本件事故当時,自家繁殖犬舎を経営し,キャバリア種の成犬22頭を飼育するなどしていた。しかし,被害者は,本件事故により傷害を負い,入通院したことから,犬の飼育をすることが困難となり,平成12年11月29日から平成13年5月10日までの間,前記の成犬22頭を,1頭当たり1日2万2157円の料金で,同犬種を専門に飼育するOに預け,合計249万円の預かり料金を支払った。なお,被害者は,キャバリア種の犬を飼育するについては一定の経費を支出していると推認されるところ,その額については必ずしも明確ではないが,少なくともその2割に相当する49万8000円を経費として控除するのが相当であると考えられる。これによれば,被害者は,飼育依頼代金として199万2000円の損害を被ったと認められる。
(名古屋地裁平成16年9月15日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>看護費等の算定において症状固定後の現価をもって損害と認定することに不合理があるとはいえないとした事例
加害者は,将来生ずるべき逸失利益や介護料等の損害の計算に当たっては,事故時から遅延損害金が付されることとの均衡から,事故時を基準としなければならない旨主張する。しかし,事故時に発生する人身傷害の一つとして算定される逸失利益及び将来の介護料の額は,裁判所において諸般の事情を考慮して合理的な相当額を定めれば足りると解されるところ,逸失利益や将来の介護料の算定に当たり中間利息をどのように控除するかという問題と,損害賠償額全体についての遅延損害金の発生の問題とは必ずしも厳密な理論的関連性があるとはいえず,実務上,逸失利益や将来の介護料の算定に,さほどの不合理があるとはいえない。また,逸失利益や将来の介護料を算定する場面においてのみ厳密な論理を適用し,事故日から症状固定日までの中間利息を控除することを求めることが相当であるとはいえない。なお,遅延損害金が単利式で計算して付加されるのに対し,逸失利益や将来の看護費については長期間にわたり複利式で中間利息が控除されることになるから,事故日から症状固定時までの中間利息を控除しないことから直ちに被害者が不当に利得するものともいえない。以上によれば,結局,加害者側の主張を採用することはできない。
(東京地裁平成16年7月13日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>被害者の平均余命までの将来の入浴費を認めた事例
被害者に入浴の必要性があることについては当事者間に争いはなく,請求額は相当範囲である。これを50%に限定すべき根拠は見つからない。
(被害者側主張)
市の入浴サービスで業者に来てもらうと一回につき2000円でサービスを受けられるが,上限は週一回であり,それを超えるものは全額自己負担となり,一回につき1万3250円かかる。週三回程度の入浴が最低限必要であり,過去分に加え,平均余命に対応するライプニッツ係数を用いて中間利息を控除すると,2007万7457円となる。
(東京地裁平成16年3月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>任意保険等は既発生の遅延損害金に充当されるとした事例
任意保険にせよ自賠責保険にせよ,いずれも被保険者が第三者に対し損害賠償債務を負担することによって被る損害を保険者が填補する責任保険であり,保険会社としては,保険契約または政令で定められた保険金額の限度で保険金を支払う義務を負うところ,被保険者が第三者に対して負担する損害賠償債務の内容は,第三者との関係で定めるものであるから,これに遅延損害金が含まれるのであれば,任意保険金であれ自賠責保険金であれ,既発生の遅延損害金債務に充当されることになると考えられる。したがって,被害者に支払われた任意保険金および自賠責保険金は,損害賠償債務の元本に充当する旨の明示または黙示の合意がない限り,民法491条により,まず既発生の遅延損害金に充当され,その残額が元本に充当されるものと解するのが相当である。本件については,任意保険会社から支払われた152万5575円と自賠責保険会社から支払われた2664万9450円について,損害賠償債務の元本に充当する旨の明示または黙示の合意があったことを認めるに足りる証拠はないから,いずれも民法491条の法定充当によるべきものということになる。
(東京地裁平成15年12月8日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>施術費について債務引受けする趣旨のものと認めた事例
共済組合(以下「被告」という)の担当者は,平成13年11月20日付の書面により,本件事故による負傷につき,被害者が柔道整復師(以下「原告」という)の施術を受けることによる施術費を,施術証明書および施術明細書を添えて,直接,被告に対し請求するよう求め,さらに,電話でこれを確認したことが認められる。被告の原告に対する申入れは,被害者の原告に対する施術費の支払債務につき,立替払いをする用意があることを予告するに過ぎないものとはいえず,適正な施術費については,被告が債務引受けをするというものであると解されるため,原告と被告との合意により,適正な施術費については,被告は,原告に対し,その支払義務を負うものというべきである。この支払は,交通事故による損害賠償義務の額が確定する前になされるもので,被告はもともとは,原告に対し直接に支払うべき義務があるわけではないのに,あえて合意により支払いをするものであることからすると,施術費の単価については,当事者間で特段の合意をしない限り,被告の定める基準によることが前提となっていたものというべきである。本件では,この特段の合意があったことについては証拠がないので,被告が原告に対して支払うべき施術費は,被告の既払金額のみであるというべきである。
(千葉地裁平成15年10月27日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>給付金について過失相殺前に損害から控除した事例
1.傷病手当金
傷病手当金の給付は,その性質から見て被害者が本訴で主張している損害と同一同質のものを対象としているということができ,その給付により被害者の損害を填補しているというべきであるから,その給付額を被害者の損害額から控除すべきである。
2.高額療養費
高額療養費の性質からみて被保険者の受けた被害を填補するものである点において,損害賠償と同一の事由の関係があり,その給付により損害を填補しているといえるものは,治療費が請求されている機関に対応する高額療養費のみであるというべきである。
3.食事療養費
食事療養費の給付は,元来対応する治療費が損害として計上され,これにつき同額の填補がされたものとして,過失相殺の処理前に控除されるべきものであるところ,被害者はこれに係る治療費を損害として主張・請求していないのであるから,本件における損害賠償額の算定上は考慮する必要がない。
4.過失相殺と損益相殺の先後
健康保険給付は被害者の過失を重視することなく,社会保障の一環として支払われるべきものであることに鑑みれば,過失相殺の負担は保険者等に帰せしめるのが妥当であるから,過失相殺前にこれを損害から控除すべきである。
(名古屋地裁平成15年3月24日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>空家賃損害を認めた事例
被害者は,平成10年4月から整骨・鍼灸院を開業する予定だったため,平成9年9月から店舗を借り,以後,月額18万円の家賃を払い続けている(店舗として最適の物件であると感じたことから,開業の半年以上前から契約して家賃を払っていた)。開業予定であった平成10年4月から休業の必要性が認められる平成10年10月15日までの間の6.5か月分の家賃については,本件事故と相当因果関係を有する損害と認められる。
18万円×6.5=117万円
(大阪地裁平成14年2月22日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>入浴介助費用等を別途に認めるとした事例
将来の介護費用としては,入浴介助等を受けている現状を前提に認定しているのであるから,被害者の請求する公的サービスを受けるための診断書作成費用,入浴介助費および交通費はそれとは別途,認められるべきである。その他の介助機材購入費は,いずれも先に認定した将来の自宅療養中の雑費に含まれるものである。
(東京地裁平成12年9月19日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>被害者の子の損害賠償請求を認めなかった事例
被害者が死亡したため,障害のある子を,他の子が介護,看護にあたらざるを得なくなったことを理由とする労働の対価相当額の損害は,被害者の逸失利益に含まれるものであり,被害者の逸失利益と別の損害として認めることはできないから主張自体失当である。
(名古屋地裁平成11年9月24日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。