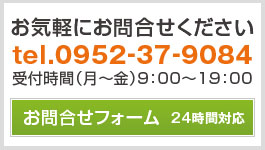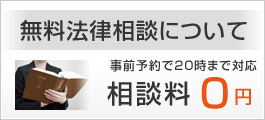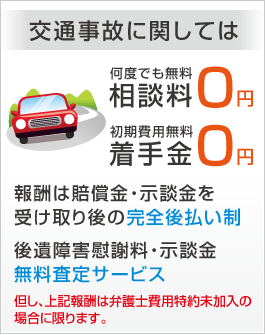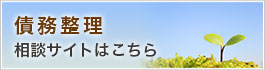Archive for the ‘未分類’ Category
「違法な取り調べで苦痛」無罪判決の男性が提訴 大阪
大阪府警による違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして、傷害事件で無罪判決が確定した堺市の男性(81)が24日、府警を所管する大阪府に200万円の慰謝料を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、男性は2013年9~11月、知人を殴って負傷させた疑いで西堺署(堺市)の任意の事情聴取を受けた際、巡査長から「やりましたって一言言うたら、すぐ済む話やで」「命令に答えろ、あほ」などと言われ、自白を強要されたと主張している。
男性側から苦情を申し立てられた府警は現在、内部調査を進めている。
(朝日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<福岡家裁>面会拒否で親権変更「父と交流実現のため」
離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男(7)と別居した40代の父親が、親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。
決定は昨年12月4日付。家裁は「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断した。
審判などによると、夫婦は関東地方に住んでいた。父親が2010年3月、東京家裁に離婚調停を申し立て、双方が長男の親権を求めた。別居し、調停中は1週間交代で長男と同居して世話(監護)することで合意したが、11年1月以降は母親が長男と住み、父親は月3回、長男と面会できるよう協議で変更した。ところが、長男が次第に面会交流を拒むようになった。
母親は11年4月、長男と福岡県内に転居。11年7月、月1回の面会交流を条件に母親が親権者となり調停離婚が成立した。しかし、面会できなかったため父親が12年9月、親権者変更を福岡家裁に申し立てた。
◇子に何が良いか「慎重に判断を」
離婚などで子供と離れて暮らす親が、面会交流を望んで家裁に調停を申し立てるケースは年々増加している。最高裁によると、昨年の申立件数は1万1312件で、10年前の約2.5倍。
一方、面会交流を認めるかどうか、慎重に判断すべきだという意見もある。
今回の審判で男性の代理人を務めた清源(きよもと)万里子弁護士(大分県弁護士会)は「家庭内暴力や虐待など、子供にとって面会交流がよくないケースもある。子供に何が一番良いか、両親双方の代理人や家裁調査官などがきめ細かく調べて判断するのが重要だ」と指摘している。
【ことば】親権と面会交流
親権は未成年の子供を養育する親の権利義務で、監護(監督・保護)や教育、財産管理などに範囲が及ぶ。民法は離婚した場合はどちらか一方が親権者になると定めるが、事情によって親権者と別に監護者を決め、親権者が財産管理、監護者が子供を養育する場合もある。面会交流は離婚などで子供と別居する親が、同居する親との間でルールを決め定期的に子供と会うこと。家庭裁判所に調停を申し立てることもできる。
(毎日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
憲法9条に平和賞を ノーベル委へ推薦状提出 神戸の団体
戦争放棄を定めた憲法9条のノーベル平和賞受賞を目指し、大学教授らでつくる「憲法9条をノーベル平和賞に推す神戸の会」(推す会)は21日、昨年に続き、ノーベル賞委員会(ノルウェー)に推薦状を提出したことを発表した。受賞対象は昨年の「日本国民」から、「日本で9条のために取り組む団体」に変更。対象を狭め、受賞の可能性を高める狙いという。
推す会は2013年12月、ノーベル賞の推薦資格がある教授らで結成。14年1月には受賞対象を「9条を保持してきた日本国民」として推薦状を送ったが受賞はならなかった。今回は、団体名を特定せず「活動するあらゆる団体」として、1月30日、111人が連名で推薦状を提出した。
推す会はこの日、神戸市中央区で会見。会長の水垣渉・京都大学名誉教授(79)は「9条は普遍的で大きな意義を持っており、全人類が共有すべき内容。受賞すれば世界中に理念が広がる」と話した。
(神戸新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
「選挙権18歳」今国会成立へ=来年の参院選から適用―有権者240万人増
共産、社民両党を除く与野党各党は18日、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案を来週中をめどに共同で衆院に再提出する方針を固めた。今国会で成立し、2016年夏の参院選以降の国政・地方選挙に適用される見通し。選挙権年齢の変更は1945年に「25歳以上」から現行の「20歳以上」に改められて以来70年ぶりとなる。
選挙権年齢の見直しは、昨年6月に成立した憲法改正の国民投票の投票年齢を「18歳以上」に引き下げる改正国民投票法を受けたもの。
公選法改正案は昨年11月、自民、民主、維新、公明の各党などにより国会提出されたが、衆院解散に伴い廃案となっていた。改正案は、施行時期を「公布1年後」としており、各党は6月24日の今国会会期末までの成立を目指す。
少年法は未成年者の刑事事件について、成人よりも軽い刑罰を規定している。しかし改正案は、18、19歳の者でも買収など連座制の対象となる悪質な選挙違反を犯した場合には、原則として家庭裁判所が検察官送致(逆送)し、成人と同じ処罰対象とする規定を盛り込んだ。
法案検討の段階では、刑事裁判の裁判員や検察審査会の審査員の選任資格についても同様に引き下げる方向だったが、「当分の間」は現行の「20歳以上」を維持することにした。
16年夏に改正法が適用される場合、有権者は約240万人増える。高校在学中に選挙権を得るケースが多くなるため、改正案に賛同する各党でつくるプロジェクトチームは今後、高校での「政治教育」の拡充について議論していく考えだ。民法に規定される成人年齢の引き下げも、引き続き協議の対象となる。
(時事通信社より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
「国民の目が厳しくなっている」大谷直人・新最高裁判事が就任会見
前大阪高裁長官で最高裁判事に就任した大谷直人氏(62)が17日、最高裁で会見し、「国民と裁判所の距離は確実に縮まっているというのが実感。
その分だけ、国民の目も厳しくなっている。気負うことなく1つ1つの事件に誠実に取り組んでいきたい」と抱負を語った。
今年5月に施行から6年を迎える裁判員制度導入にあたり、最高裁刑事局長時代に制度設計に携わった。
大谷氏は「7500件を超える裁判員裁判が実施されてきた。国民参加の特殊な裁判とみられがちだが、最も重い犯罪が裁判員裁判で裁かれている。特殊な裁判という意識から自由になることで、柔軟な運用が行われていくのではないか」と指摘。
「法曹三者がそれぞれ自分たちの活動を振り返り、その内容を持ち寄って議論を深める必要がある」と感じているという。
14日に定年退官した白木勇氏の後任。東大出身で昭和52年、判事補。最高裁事務総長を経て、平成26年7月から大阪高裁長官を務めた。
(産経新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
柔道の練習中に「中1死亡」 技をかけた「元顧問」の賠償責任はナシ――なぜか?
柔道部の練習で技をかけられた中学生が死亡したが、技をかけた元顧問の「賠償責任」は認められなかった——。滋賀県愛荘町の町立中学校で2009年7月、柔道の練習中に中学1年の男子生徒が死亡した。この事故について、中学生の母親が柔道部の顧問だった男性に損害賠償を求めていたが、最高裁は2月5日の決定で、母親の訴えを退けた。
これにより、町の責任を認めつつ、元顧問の「個人責任」は認めなかった一審・二審の判決が確定した。報道によると、この訴訟では、一審の大津地裁が町に対して約3700万円の支払いを命じたが、元顧問への請求は「公務員の過失は町が責任を負う」として退け、二審の大阪高裁もこの判決を支持した。一審・二審の判決によると、生徒は元顧問に返し技をかけられて倒れ、約1カ月後に急性硬膜化血腫で死亡した。
遺族側は「私立学校では教師の個人責任が問えるのに、公立で問えないのは不合理だ」と主張していたという。なぜ今回、元顧問ではなく、町に損害賠償が命じられたのか。元顧問の「個人責任」を問うことはできないのか。公立小学校での教員経験がある畑中優宏弁護士に聞いた。
●公務員個人には賠償責任がない
「この裁判で、元顧問個人ではなく、町に損害賠償が命じられた理由は、国家賠償法が適用されたからです」
畑中弁護士はこのように切り出した。国家賠償法とは、どのような法律なのだろうか。
「国家賠償法とは、国や公共団体の損害賠償について適用される法律です。国公立の学校にも適用されます。この法律では、公務員が不法行為をした場合、国や自治体が賠償責任を負い、公務員個人は、賠償責任を負わないとされています。ですから今回のケースも、公務員である元顧問個人に賠償責任を負わせることはできません」
●私立学校の場合は賠償責任を負う
国公立の学校の教師個人には、直接的には損害賠償責任を負わせられないという。では、私立学校の場合はどうなのか。
「私立学校では、民法が適用されます。したがって、教師個人が賠償責任を負い、さらに学校も賠償責任を負います」
同じ教師でありながら、なぜ国公立と私立で、このような違いがあるのだろう。
「国公立と私立とでは、教師の根本的な立場が違うからです。国公立の学校の教師は公務員であるため、彼らの行為は、あくまで公権力の行使の一環として考えられています。一方、私立学校の教師の行為は、公的な立場を離れた一個人の行為と考えられています。
今回のケースでは、公務員である元顧問個人は賠償責任を負いません。ただ、元顧問の不法行為に故意または重大な過失があると町が判断すれば、町が遺族に損害賠償をした上で、さらに元顧問に求償することができます。ですから、間接的に、元顧問の賠償責任を問うことはできるといえるでしょう」
畑中弁護士はこのように語っていた。
(弁護士ドットコムニュース)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
厚生年金基金、290基金が解散予定 9割積み立て不足
社員らが入る厚生年金基金のうち、2014年末時点で290基金が解散を予定し、その9割にあたる261基金が13年度末時点で企業年金の積み立て不足に陥っていることがわかった。
261基金の年金受給者と現役社員の加入者は計306万人にのぼる。積み立て不足を穴埋めできずに解散する基金では、企業年金がなくなったり減額されたりするおそれがある。
厚生労働省のモデル例では、厚生年金基金の企業年金は月に7千~1万6千円になっている。企業年金を受け取る期間は10~20年の人が多く、支給されなくなれば「最大で数百万円の権利を失う」(神奈川県の基金)という人もいる。
朝日新聞は厚労省がまとめた資料を入手した。厚生年金基金は昨年末時点で483基金あり、このうち290基金が解散を予定していた。
(朝日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<逆転無罪>「女性の証言は信用できない」と男性会社員に
◇強制わいせつ致傷罪事件で大阪高裁判決
バーで女性店員にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ致傷罪に問われた京都市伏見区の男性会社員(42)の控訴審判決で、大阪高裁は13日、懲役2年(求刑・懲役4年)の実刑とした裁判員裁判の1審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。笹野明義裁判長は「女性の証言は全体的に信用できない」と述べた。
男性は2013年6月、客として訪れた京都市下京区のバーで、閉店時間を過ぎていたため女性店員に退店を求められたことに憤慨。カウンターを両手でたたき、女性を押し倒して足に約1週間の打撲を負わせたとして起訴された。男性は無罪を主張していた。
判決は、バーのカウンターに残されていた男性の掌紋の付き方が、女性の証言と異なると指摘。下半身を触られたとする女性の供述も「捜査段階と変遷し、誇張している可能性がある」とした。
1審は掌紋について女性の証言通りに付いていたと認定。しかし、大阪高検が再捜査した結果、1審の証拠が誤っていたことが判明し、検察側は控訴審で「遺憾の意を表明する」と述べていた。
(毎日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
戦闘ヘリ訴訟、国が上告=350億円支払い命令で
戦闘ヘリコプターの導入をめぐり、計画途中で発注を打ち切られた富士重工業が初期投資費用約350億円の支払いを国に求めた訴訟で、国は12日までに、全額支払いを命じた東京高裁判決を不服として最高裁に上告した。上告は10日付。
訴訟では、米ボーイング社へのライセンス料などの初期費用について、防衛省側が負担する合意が成立していたかどうかが争点だった。
一審東京地裁は「合意は成立していなかった」として請求を退けたが、東京高裁は先月29日、「受注業者との間では、防衛省が負担することが当然の前提とされていた」と指摘。国の信義則違反を認めて支払いを命じた。
(時事通信社より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
「法定利率」を5%から3%に…民法改正要綱案
法相の諮問機関「法制審議会」の民法部会が10日、民法の債権に関する規定を抜本的に見直す要綱案を決定した。
民法に「約款」に関するルールを新設することなどを打ち出した。24日の法制審総会で法相に答申する予定。
民法の債権に関する条文の抜本改正は、1896年の民法制定以来、初めて。要綱案には、飲食店での未払い金(ツケ)の時効期間延長など約200の見直し項目が盛り込まれており、約款以外の項目は、昨年8月にまとまっていた。法務省は一連の見直し内容を反映した民法改正案を今国会に提出する。
これまで民法には約款に関する規定がなく、約款が契約内容として有効と認められる要件があいまいなままとなっている。インターネット通販などでは、消費者が約款を十分理解しないまま商品を購入し、届いた商品に不満があっても、約款で返品が認められないなどのトラブルが相次いでいた。
これまでも不当な内容の約款は裁判で無効とされてきたが、要綱案は、消費者保護の立場を強化する観点から、民法を見直すことにした。約款が有効と認められるには、〈1〉企業と消費者の間で、約款を契約内容とすることで合意する〈2〉企業が約款を契約内容とすることをあらかじめ表示する――のいずれかを満たす必要があるとした。ネット通販の場合であれば、企業は契約成立前の段階で、消費者に約款を読んだうえで同意するむねをクリックしてもらうなどの手続きが必要になる見込み。
消費者の利益を一方的に害する内容の約款は認めないことや、約款の変更は消費者にとって利益になる場合に限ることなども打ち出した。
法制審議会の民法部会は2009年から民法の見直しを検討しており、昨年8月、約款以外の約200項目を見直した。未払い金の債権消滅の時効期間について、飲食代(1年)、弁護士費用(2年)、病院の診療費(3年)を5年に延長することなどが柱だ。
見直しでは、賠償金に上乗せする遅延利息などに適用される法定利率(5%)が市場金利に比べて高すぎる現状を踏まえ、3%に引き下げたうえで、市場金利の実勢を踏まえて3年ごとに見直す変動制を導入する。
賃貸住宅契約では、借り主が経年変化による物件の原状回復義務を負わないことや、大家による敷金返還規定を明記する。安易に銀行融資の保証人となった第三者が、多額の借金返済を求められて生活破綻に追い込まれないよう、公証人が保証意思を確認することも義務づける。
(YOMIURI ONLINEより)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。