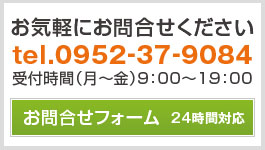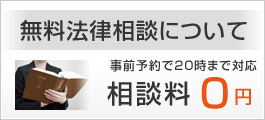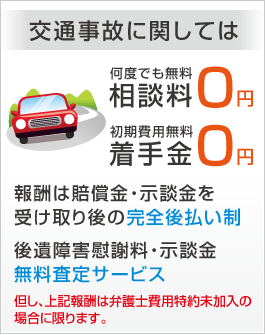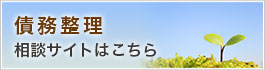Archive for the ‘未分類’ Category
自公政調会長、少年法改正に言及 川崎の殺害事件受け
自民党の稲田朋美政調会長と公明党の石井啓一政調会長は27日の記者会見で、川崎市の中学生殺害事件で未成年が逮捕されたことを受けて、未成年の刑事事件の手続きなどを定めた少年法の改正の必要性に言及した。対象年齢を20歳から18歳に引き下げたり、加害少年の氏名を報道することを禁じる規制を見直したりする可能性を示した。
石井氏は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しになっていることから、民法改正で成人年齢も引き下がった場合「少年法の年齢を合わせるべきだとの議論も当然起きてくるだろう」と述べた。稲田氏は「少年が加害者である場合は名前を伏せ、通常の刑事裁判とは違う取り扱いを受ける」と指摘。その上で「(犯罪が)非常に凶悪化している。犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか、今後課題になるのではないか」と語った。
(朝日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<群馬県警>交番内でセクハラ 女性警察官3人の体触る
◇40代の男性巡査部長、巡査に降格
群馬県警の交番に勤務する40代の男性巡査部長が交番内などで、女性警察官3人の体を触るなどのセクハラを繰り返したとして、県警が停職6カ月の懲戒処分にしたことが28日、県警への取材で分かった。県警は巡査部長本人から申し出を受け、巡査に降格させた。
県警監察課によると、元巡査部長は昨年、交番内や職場旅行の宴席で、女性3人にセクハラ行為を1回ずつした。うち1人が上司に相談した。3人からは被害届が出されておらず、県警は刑事事件としての立件は見送った。
処分は1月23日付で、県警は公表していない。県警は「3人から公表を控えてほしいとの強い要望があった。プライバシー保護を尊重した」と説明している。
同県警では、小学4年の女児(10)を誘拐しようとしたとして、吉岡町交番勤務の巡査の男(24)が今月18日に逮捕されたばかり。
(毎日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<接見交通権>「画像撮影は含まれず」地裁小倉支部判決
福岡拘置所小倉拘置支所(北九州市小倉北区)で接見中に撮影した被告の画像を支所側の要請で消去させられたのは接見交通権の侵害に当たるとして、福岡県の田辺匡彦(まさひこ)弁護士(61)が国に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は26日、請求を棄却した。田辺弁護士は控訴する方針。
野々垣隆樹裁判長は「撮影は接見交通権に含まれず、面会室での撮影禁止が弁護活動を不当に制約するとまでは言えない」と述べた。
判決によると、田辺弁護士は2012年2月、被告に「支所職員から暴行を受けた。証拠に残してほしい」と言われ、携帯電話のカメラ機能で被告の顔を撮影したが、支所職員に消去を求められ、その場で画像を消去した。
田辺弁護士は判決後「撮影に伴う拘置所側の弊害すら示しておらず、極めて不当な判決」と話した。法務省は「国の主張が認められたと理解している」としている。
接見時の写真撮影の適否を巡る判決は昨年11月の東京地裁に続き全国2例目。東京地裁は「被告らを撮影して記録することは必要不可欠とまでは言い難い」と判断した一方、途中で面会を中止させた行為は接見交通権の侵害に当たるとして国に10万円の賠償を命じた。
(毎日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
言葉のセクハラ 厳格な処分を支持した最高裁
度を越した従業員のセクハラ発言に、企業が厳格に対応するのはもっともだ――。最高裁の明快なメッセージだろう。
女性従業員にセクハラ発言を繰り返した男性社員2人に対する懲戒処分を巡り、最高裁は処分を妥当だとする判決を言い渡した。
大阪の水族館運営会社で課長代理を務めていた2人は、部下の女性に「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「夜の仕事とかせえへんのか?」といった言葉を度々発した。
露骨な性的話題を口にすることもあったという。
会社は、2人を30日間と10日間の出勤停止処分としたうえで、係長に降格させた。
最高裁は、「強い不快感や嫌悪感、屈辱感を与え、執務環境を著しく害した」と、一連の発言の悪質性を認定した。
体への接触の有無にかかわらず、性的な言動で相手を不快にさせることは許されない。そんな警告と捉えることもできる。
1審の大阪地裁は、会社の処分を支持した。2審の大阪高裁は逆に、処分を無効と判断した。
高裁は、女性が明確に抗議しなかったことから、2人は自分たちの発言が許容されていると受け止めたと認定した。これを踏まえ、処分が重すぎると結論付けた。
セクハラへの理解を欠いた判断だったと言わざるを得ない。
最高裁は、セクハラの被害者について、「職場の人間関係の悪化などを懸念し、抗議や抵抗、会社への申告を 躊躇 ちゅうちょすることが少なくない」という点を重視した。実態を的確に捉えている。
ハラスメント被害に対し、「我慢した」「諦めて仕事を辞めた」という女性は、それぞれ3割前後に上るという調査結果もある。
2人は、職場のセクハラ防止に努めるべき管理職の立場にあった。それにもかかわらず、悪質な発言は1年余りにも及んだ。
こうした状況を考えれば、最高裁が、処分無効を求めた2人の訴えを退けたのは、当然である。
2007年に施行された改正男女雇用機会均等法は、相談体制の整備など、必要な措置を講じるよう事業主に義務付けた。運用指針では、厳正な対処を就業規則に定めることも求めている。積極的に取り組んでいる企業は多い。
だが、言葉のセクハラを軽視する風潮は、一部に根強く残っているのも事実だろう。最高裁判決を機に、セクハラに対する意識改革をさらに進めたい。
(読売新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
元警部補、収賄も有罪=捜査情報漏えい事件―福岡高裁
暴力団関係者に捜査情報を漏らし現金を受け取ったとして、収賄や地方公務員法違反などの罪に問われた元福岡県警警部補中村俊夫被告(51)=懲戒免職=の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。林秀文裁判長は、収賄について無罪とした一審福岡地裁判決を破棄、有罪と認定し懲役2年6月、執行猶予5年を言い渡した。
また、贈賄罪に問われた暴力団関係者の男2人の一審無罪判決も破棄し、審理を同地裁に差し戻した。
一審判決は収賄について、「被告の捜査段階の供述は取調官の誘導に迎合したことが否定できず、信用できない」としたが、林裁判長は「供述内容に不自然な点や不合理な点はなく、客観的な裏付けもあり信用性は高い」と判断した。
(時事通信社より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
強姦事件の再審決定 診療記録、証言と矛盾 大阪地裁
強姦(ごうかん)されたという女性の訴えとは矛盾する診療記録があったのに、女性の証言をもとに起訴された男性の裁判で審理対象になっていなかったことがわかった。無罪を主張した男性の実刑判決が確定し、服役中に診療記録の存在が判明。大阪地検が昨年11月に刑の執行を停止する異例の措置につながった。大阪地裁(登石〈といし〉郁朗裁判長)は27日、「無罪を言い渡すべき新証拠がある」とし、再審開始の決定を出した。
関係者によると、男性は大阪市内で2004年と08年に同じ女性を襲い、同年にもこの女性の胸をつかむなどしたとして強姦と強制わいせつの罪で逮捕、起訴された。男性は「やっていない」と主張したが、09年の大阪地裁判決は懲役12年の実刑を言い渡した。大阪高裁が控訴を棄却し、11年には最高裁が上告を退けて確定した。
その後、控訴審で弁護を担当した弁護人が女性や事件の目撃者とされた家族から聞き取り調査。2人が確定判決の根拠となった被害証言を「うそだった」と翻したため、昨年9月に再審を請求した。地検も2人が虚偽の証言をしていたことに加え、「男性が事件に関与していないと示す『客観的証拠』も確認した」として、昨年11月18日に男性の刑の執行を止めて釈放したと発表した。男性の服役は約3年6カ月に及んだ。
(朝日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
「威圧され適応障害」…看護師長のパワハラ認定
北九州市小倉北区の「新小倉病院」に看護師として勤めていた女性(30歳代)が、元上司によるパワーハラスメント(職権による人権侵害)で適応障害になったとして、運営する国家公務員共済組合連合会(東京)や元上司の看護師長を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁小倉支部であった。
北村久美裁判官は、看護師長の言動を「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定、被告に約120万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性は病院に勤務していた2013年4~5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に早退を申し出た。
看護師長は、女性の有給休暇が残っていたが、「もう休めないでしょ」「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。女性は、ミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠になり、同11月に適応障害と診断されて休職。昨年3月退職した。
(読売新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
【民法改正】法定利率引き下げ、敷金…大刷新を“初めの一歩”に
明治時代に制定されて以来となる民法・債権分野の大改正。法相が法制審議会に改正を諮問した目的の一つは、「社会・経済の変化への対応」だった。制定から約120年の時を経て時代遅れになった条文を刷新する。
例えば、法定利率の引き下げだ。これまでは年5%だったが、低金利時代にはそぐわない。3%に引き下げた上で、市中金利を反映する変動制を導入する。時代に合った納得性の高い改正内容といえるだろう。
もう一つの目的は「国民への分かりやすさ」で、好例は敷金の定義だ。アパート入居時に大家に預けた敷金から転居時に差し引かれる「原状回復費」をめぐって嫌な思いをした-という経験を持つ人は少なくないはずだ。改正では敷金を「家賃の担保」と定義し、「原状回復に経年変化は含まない」と定める。基本法である六法の一つの民法に明記することで、消費者トラブルの回避につながる。
法制審・民法部会は伝統的に「全員一致」を原則とする。民法は国民生活に密接に関連するため、より厳密なコンセンサス(合意)を得る必要があるからだが、各界の代表者からなる部会の議論などを経て、改正項目は当初の半分以下に減った。それでも、全員一致を貫いたからこそ、約款規定に反対していた経済団体も最終的に5年間の議論をご破算にはできず、改正要綱に賛成した。
弁護士団体幹部は「改正要綱は良い意味でも悪い意味でも“妥協の産物”かもしれないが、初めの一歩。今後、さらなる改正を続ければいい」と話していた。
(産経新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
法相が民法相続分野見直しを法制審に諮問「配偶者の貢献」考慮
上川陽子法相は24日、配偶者に配慮した相続法制のあり方について検討するよう法制審議会に諮問した。法制審は、法務省の有識者からなる「相続法制検討ワーキングチーム(WT)」が1月にまとめた報告書を基に、民法(相続分野)の改正を視野に入れて議論する。
報告書には、(1)配偶者の居住権を保障する(2)他の相続人に比べて大きな介護の貢献を遺産相続に反映させる(3)実質的な夫婦共有財産については配偶者の取り分を増やす-などが提示されている。
WTは、法律上の夫婦の子(嫡出子)と結婚していない男女間の子(婚外子)の相続分が同等となる民法改正案が平成25年12月に国会で可決されたことを受け、自民党が「日本の伝統的な家族像が壊れる」などとして配偶者の保護を検討するよう同省に要請したことから設置された。
(産経新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
民法の契約分野、120年ぶり抜本改正を答申
法相の諮問機関「法制審議会」は24日の総会で、民法の債権に関する規定を抜本的に見直す要綱を決定し、上川法相に答申した。
企業や個人の契約ルールなどを定めた債権関係規定の大幅な見直しは、1896年(明治29年)の民法制定以来初めて。インターネット通販や保険などの契約で事業者が消費者に示す「約款」に関する規定の新設や、法定利率の変更などが柱だ。法務省は3月末に同法改正案を国会に提出する。
要綱の改正項目は約200に及ぶ。民法制定から約120年の間に生じた、社会や経済情勢の変化に対応する内容を盛り込んだ。
事業者が不特定多数の消費者と画一的な条件で契約する際に用いる約款は現在、法的な位置付けが曖昧だ。買い手がほとんど読まずに契約し、後でトラブルになるケースも多い。要綱では、事業者があらかじめ約款に基づく契約であることを表示していれば、消費者が約款を理解していなくても合意したと見なすとした。だが、消費者の利益を一方的に害する項目は無効とするとの規定も設けた。
(読売新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。