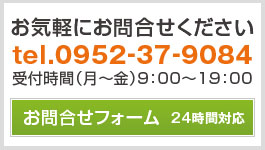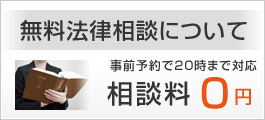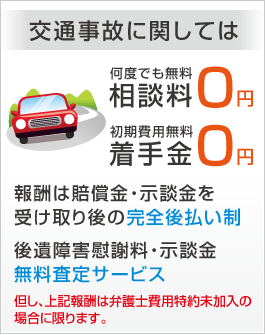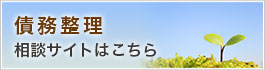Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士・交通事故裁判例>健康保険診療を求められた療育取扱機関は,これを拒むことができず,保険診療による義務があると認定された事例
国民健康保険の保険者は,被保険者に法定の保険事故が発生した場合は,療養給付を行う義務を負い,その事故の発生原因についてはこれを問わないのが原則であって,その例外は,いわば社会的に避難されるべき泥酔,著しい不行状による交通事故にのみ適用される。
療養取扱機関は,患者から被保険者証を提出され,保険診療を求められたときは,これを拒むことができず,保険医は,医学的,経済的,社会的に適正な診療を行う義務がある。初診日以降,被保険者証が提出されるまでは,自由診療契約が成立しているというべきであるが,提出後はそれを招来にわたって解除する旨の黙示の意思表示あるものと解される。
保険診療を受ける権利は,受益者においてこれを招来にわたって放棄することが可能だが,病院事務局長が「保険扱いにすると充分な治療・看護ができない。」旨勧告し,かつ被保険者証を返還されたことが契機となって一旦は切替えを断念した時期があったものの,最終的には,再度被保険者証を提出した本件では,勧告内容が不適切なもので,これに基づく断念の意思は法律上無効というべく,保険診療を受ける権利を放棄したと認めることはできない。
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>頚椎捻挫の治療として,1週間の入院治療費のみが事故と相当性ある損害と認定された事例
A,B,Cらの診療内容と本件事故の態様,その衝撃の部位程度,事故前後の経緯,状況,前認定の診療上の多くの問題点,本件事故当時における頚椎捻挫の一般的治療方針,状況,その他諸事情に照らした場合,Aら3名につきその症状は,通常の頚椎捻挫の域を超えるものとは認めがたく,病院の治療方法,治療期間のうち,特に入院治療の期間が長期にわたっていること,またレオマデックスの点滴静注が施行されていることにつき,医師としての個別の治療行為における裁量的な幅といったものを十分考慮に入れるとしてもなお通常の治療方法,期間としての合理的な必要性を肯認しがたく,前記各認定の諸事情に照らした場合,Aら3名につき,いずれも少なくとも1週間を超えての入院およびレオマデックスの使用については,本件事故との相当因果関係を肯認しがたいものといわざるを得ない。その他の診療内容には過剰診療の感もないではないが,頚椎捻挫の治療行為の特殊性,個別性,また医療行為のある程度の裁量性等を考慮に入れるとき,本件事故との相当因果関係を否定することは困難なものといわざるを得ない。
(広島地裁昭和59年8月31日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>病院から保険会社に対する診療費請求につき,1点単価を20円とするのが相当であると判断した事例
治療期間は,当初1点単価を25円として計算のうえ保険会社に請求していたところ,入院料だけは1点単価を20円にしてほしい旨保険会社から申入れがあってこれに応じ,さらにその後,一つの事故で被害者が3人もいて,診療費が総額的に高くなるから,その余の分についても1点単価を20円にして請求してもらえれば支払もスムーズにいく旨保険会社から,再度の申入れがあってこれにも応じたところ,そのうち本件事故が保険金詐取を目的とするものであることが明らかになったため保険会社はその支払をせずに現在に至っていることが認められ,かかる経緯からすれば1点単価を20円として計算のうえ治療費額を算出するのが相当である。たとえ,保険指定医の指定を受けていたとしても,かかる特別の事情が認められる以上,1点単価を10円として計算するのが妥当であるとは考えられない。
(神戸地裁昭和59年8月28日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>事故後2年以降の治療と事故との相当因果関係を否定した事例
治療中断後昭和53年10月以降の入通院治療については,昭和54年4月から約2か月にわたってT大学病院において受けた各種検査の結果,異常がなく,担当医師が,事故後の経過,検査結果等を踏まえ,「2年位前症状固定となり治療終了の処理をはっきりしなければならなかったと思われる。」との診療検査所見を下していること等の事実に照らして考えると,昭和53年以降の入通院等と本件事故との間の相当因果関係を推認することは難しい。
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>過剰診療・過誤診療であった場合,特別の事情がない限り,治療は事故と相当因果関係があると判示した事例
仮に,被害者の受けた治療が過剰診療,過誤診療であったとしても,被害者においてこれを認識してあるいは少なくとも認識しなかったことに過失があって当該診療を受けたというような特別の事情がない限り,その診療は,本件事故と因果関係のあるものというべきである。そのような特別な事情の存在を認めさせるに足りる資料はない。したがって,被害者に対する治療は,本件事故と因果関係があるものというべきである。
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>高額治療費の請求につき,健康保険基準の2倍を限度に事故と相当因果関係ある損害と認めた事例
事故と治療との相当因果関係の判断に当たっては,当該治療行為の必要性および当該治療行為に対する報酬額の相当性が検討の対象となるが,本件の治療行為についてはその必要性に疑問をいだかせるような事情は見当たらない。
本件診療機関の治療費は,健康保険基準による治療費と比較すると投薬料については,12.5倍,注射料については12倍,全体としても10.4倍にのぼっていることが認められるが,自由診療の場合の社会一般の常識的な診療費水準は,健康保険の2倍程度であることが窺われる。
治療内容や治療を受けるに至った経緯等から高額診療費であっても,加害者に負担させるのを相当とするような特別の事情は本件に存しないこと明らかであるから,損害の公平な分担の見地からその全額を本件事故と相当因果関係のある支出であるとは到底認め得ない。被害者の受傷の程度,治療内容,回数,社会一般の診療費水準等諸般の事情を考慮すると,健保基準の2倍の金額(初診料および再診料は,医師会標準料金)が本件事故と相当因果関係がある。
(東京地裁昭和51年3月25日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>被害者が転医を繰り返し,治療が長期化した事情を斟酌して損害額を算定した事例
被害者の病名が変転するのは,各病院において被害者の損傷部位を頚椎,脳,脳幹のいずれの観点から診断したのかの医師の見解の相違に起因するものと推認でき,被害者の愁訴も頸部ないし頭部打撲によって発生する多彩な症状の域を出ず,日時の経過により症状も変化をきたすことを勘案すると矛盾しているとか不合理であるとまではいえないし,慢性化した神経症状が心因的要素により持続,増幅することはあり得るが,同精神薬の使用や精神療法が採られた形跡はなく,他に心因性と認めるに足りるっ証拠はない。
しかし,被害者の治療経過に照らすと,被害者は必要以上の転医を繰り返し,その結果,諸検査が重複して行われ治療費が必要以上に拡大し,結果的に治療が長期化していることは否めない。
(東京地裁昭和49年10月29日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
【サッカーボール訴訟】子育てから認知症介護まで…判決の影響大きく
無条件に認められてきた子供の行為に対する親の監督責任について、最高裁は9日の判決で「危険性のない行為による偶然の事故について親は責任を負わない」と風穴を開けた。被害者救済に重きを置いていた監督責任をめぐる損害賠償の流れが、この判決を機に変わる可能性がある。
子供に対する監督義務を定めた民法規定では、義務を尽くした親の賠償責任を問わないとする例外を設けているが、ほぼ無視されてきた。このため、子供による偶発的事故に関し、普通の子育てをしている親に責任を負わせてきた。
今回の最高裁判決は両親について「危険なことをしないよう普通のしつけをした。結果の予測は不可能」と冷静に判断。一般的な子育ての実態と裁判実務の乖離(かいり)の修正を試みた。
監督責任が問われる可能性があるのは子供の親だけではない。最高裁では現在、徘徊(はいかい)の症状がある認知症の高齢者が線路内に進入し、列車にはねられて死亡した事故をめぐり、事業者側が損害賠償を求めた訴訟が上告中で、介護現場の実態をどう見るのかが注目されている。子育てから認知症介護まで、周囲の人間はどこまで責任を負うべきなのか。今回の判決が与える影響は大きい。
(産経新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
酒気帯び運転で有罪の下鴨署員を停職6カ月 本人は依願退職 京都府警「警察官として言語道断」
酒気帯びで乗用車を運転したとして、京都府警は9日、下鴨署警務課の男性巡査部長(56)=道交法違反(酒気帯び運転)罪で罰金30万円=を停職6カ月の懲戒処分とした。巡査部長は同日、依願退職した。
府警監察官室によると、巡査部長は2月6日夜、同署の柔剣道大会の慰労会で約2時間飲酒し、帰宅後に同府向日市の自宅付近で酒気帯びで乗用車を運転した。
片山勉首席監察官は「警察官として言語道断。府民に深くおわびする」とコメントした。
(産経新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。
両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。
民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。
事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。
(朝日新聞より)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。