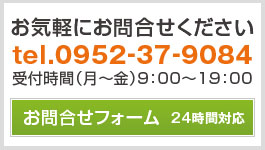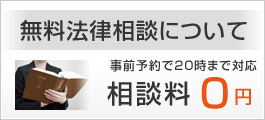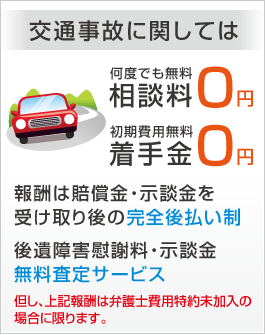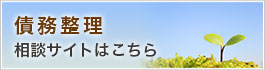Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士交通事故裁判例>医師2名への謝礼5万円を損害と認めた事例
被害者は,手術に際し,2名の医師に対し,5万円の謝礼を交付したことが認められる。そして,右の謝礼は,本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。
(東京地裁平成11年11月30日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>医師への謝礼5万円を損害と認めた事例
傷害内容,入院期間等によると医師への謝礼5万円につき,本件事故と相当因果関係がある損害と認める。
病院に6万1800円相当の車椅子を寄付したことが認められるが,これは,病院に対する感謝の気持ちの発露というべきで,医師の謝礼のほかに本件事故と相当因果関係がある損害と認めることができない。
(東京地裁平成10年1月30日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>医師等への謝礼36万円を損害と認めた事例
原告は医師,看護婦等への謝礼として39万9618円を支弁したことが認められ,これは被害者の症状に照らすと必要かつやむを得ない支出と認めるのが相当であり,これは被害者について生じた損害とするのが相当である。
(浦和地裁平成4年8月10日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>医師への謝礼15万円を損害と認めた事例
医師への謝礼中,被害者の症状,治療状況その他の諸般の事情を考慮して15万円を損害と認める。
(東京地裁昭和61年12月18日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について1日2000円で認めた事例
被害者の後遺障害の中で,特に高次脳機能障害による状態として記憶障害,地誌的障害,感情障害が出ており,被害者が日常生活を送るためには一定の場面で看視・声掛けを行う必要がある。実際にも,①被害者が笹井なことで感情を爆発させて娘らを激しく怒るので,妻が娘らの言動に気を使うとか,②火を使う炊事を被害者が行うと,消し忘れたり使い方を誤ったりする危険が高く,必ず妻が付いてなければならないとは,③被害者の行き慣れていない場所に行かなければならないときは,自分がどこにいるのか判らなくなったり,帰途が分からずパニックになったりするので,必ず妻が付き添わなければならないとか,④暗証番号などを忘れてしまうので,銀行の諸々の手続を1人で行うことはできないといった状況であり,被害者が日常生活を送るに当たり,妻の看視・声掛けが日常的に必要となっている。被害者には,近親者の看視・声掛けを行うために絶えず付添介護が必要ということになるが,その費用額は,被害者の後遺障害の程度も考慮して,1日当たり2000円をもって相当とし,被害者の平均余命年数33年のライプニッツ係数を乗じて中間利息を控除する。
(大阪地裁平成20年5月29日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>併合2級の症状固定時26歳男子の将来介護費として母親が67歳に達するまでは1日3500円,その後平均余命に相当する期間は1日1万5000円で認めた事例
被害者は,症状固定後も就労は不可能であり,社会適応力に欠けるものの,日常生活はおおむね独りでこなせること,親しい者以外に対して暴力を振るう具体的危険性までは認められないことから,常時の介助はもとより,常時の看視,声掛けをするまでの必要はないものと認められる。そうすると,被害者については,随時看視や見守りが必要な状況にあると認められる。また,現況では,被害者の介護は,すべて母親または父親が行っているものの,介護の負担が過重になりつつあり,相当な精神的負担もあるものと考えられる。以上によれば,被害者の症状固定後母親が67歳に達するまでの9年間は,近親者による介護が実施されることを原則とし,一部職業介護人による介護が併用されることを想定し,母親が67歳に達した後被害者が平均余命に相当する期間までは,専ら職業介護人による介護が実施されるものと想定することが相当である。前者については1日3500円,後者については1日1万5000円として算定することを相当と認める。
(大阪地裁平成20年4月28日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>併合4級の症状固定時32歳女子の症状固定後の付添費として,1日1000円で認めた事例
症状固定前の被害者の症状からすると,被害者には記憶障害や遂行機能障害等があり,電車に乗り間違えたりすることはあるものの,基本的には単独で外出ができており,基本的な日常生活動作は自立しており,単身での生活も可能であったことからすると,被害者に求められる付添介護の内容は,随時の看視・声掛けで十分であり,常時被害者がそれらを必要とするものではない。そして,被害者がかかる介護を要する場合は限られ,毎日,継続的に介護が必要であるとは認められない。被害者には,その生活環境の変化によっては,職業介護が必要になることがないとはいえないとしても,その介護内容や頻度に見合う,本件事故と相当因果関係のある将来の付添費は,平均すれば,1日当たり1000円とみるのが相当である。そして,付添介護が必要な期間は,症状固定時の平均余命である54年とみるのが相当である。
(東京地裁平成20年3月19日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>左前腕骨骨折等受傷の症状固定時36歳男子の家族介護料について,入院中および退院後も手を動かすことができない期間(333日)を日額5000円で認めた事例
被害者の入院しており,傷害の内容に照らすと,上記期間については介護の必要性が認められる。また,退院中も創外固定具をつけており,手を動かすことができず,着替えられない状態であったことからすると,上記期間についても介護の必要性が認められる。さらに,11月13日から創外固定具を使用しなくなったとはいえ,直ちに手を動かせる状態に戻ったわけではないことからすると,被害者が主張するように12月31日までの間についても介護の必要性が認められる。そして,1日当たりの介護費については,上記の期間を通じて5000円と認める。
(東京地裁平成20年1月28日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>高次脳機能障害の症状固定時43歳男子の将来の付添介護料について日額5000円で平均余命まで認めた事例
被害者は,日常生活において,食事,着替え,入浴,排泄等を基本的に他人の介助によらずに行うことが可能であるが,被害者の妻が,被害者に対して,食事や着替え等の準備をする必要があるほか,日常生活のほぼ全般にわたって随時声掛けを行って行動に出ることを促す必要があり,また,食事の量,火の取り扱い,金銭管理等について注意することなども必要であることからすれば,親族による付添が必要であると認められ,その額については,必要とされる付添の内容としては声掛けおよび看視が中心であることからすれば,平均余命期間(37年間)の全期間を平均して,日額5000円をもって相当と認める。
(東京地裁平成20年1月24日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士交通事故裁判例>1級1号の症状固定時21歳女子の将来の介護費用について最初の21年間は日額9000円,その後平均余命まで日額1万8000円で認めた事例
被害者の介護(入浴以外)については,両親が行っているところ,自宅療養開始後,母親が67歳に至るまでの21年間は近親者による付添介護で,その費用は日額9000円,その後,被害者が83歳に至るまでの41年間は,職業付添人による付添介護が行われることが推測されるところ,その費用は日額1万8000円が相当である。被害者の入浴については,公的支援による2名のヘルパーが介護しており,自宅療養開始後,被害者が83歳に至るまで日額814円の支出が見込まれる。
(大阪地裁平成19年12月10日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。