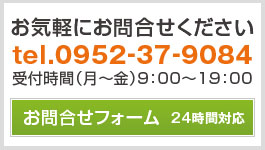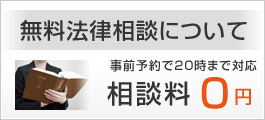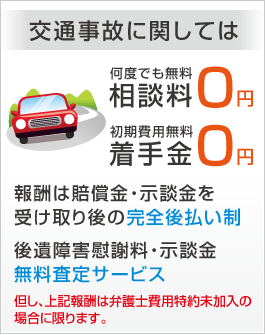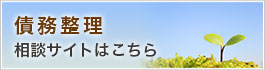Archive for the ‘未分類’ Category
<弁護士・交通事故裁判例>植物状態の18歳男子の症状固定までの付添費用として職業介護費の他に母の付添費用として日額6000円を認めた事例
症状固定まで,職業付添人のついた424日は312万3101円,職業付添人のついていない727日に母の付添いが必要であったとして日額6000円で認定
被害者は生存する限り付添看護が必要であること,母は持病の関節リウマチのために十分な付添いができないこと,被害者の症状がわずかかつ快方に向かっていることなどの事情を勘案すると,職業介護人の付添交通費を日額1000円,付添費用は1日8時間とみて日額1万2000円の限度で相当
平均余命までライプニッツ係数を用いて計算
(横浜地裁平成8年2月15日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>母親が勤務していた会社を休業・退職し事故により受傷・入院した娘の付添看護に当たった場合に,月収19万円をもって付添看護費とすることを認めず,日額4500円の付添看護費を認めた事例
A病院に入院した49日間につき母親による付添看護を要し,この間の付添費は22万0500円(4500円×49)が相当である。
母親は,本件事故のため,勤務していた会社を休業・退職して原告の看護に当たったこと,当時の母親の平均月収が19万円であったことが認められるものの,右額をもって付添費と認めることはできない。
B病院およびC病院においては,現に付添看護をなしているが,完全看護の病院であり,被害者の症状,年齢等に照らし右両病院入院中の全期間(394日)を通じて日額2000円の付添看護費を認めるのが相当である。
被害者はベッドから車椅子への移乗,段差のある箇所での車椅子移動,立位動作等に介助を要する状態にあり,日額3000円で平均余命期間をホフマン式計算法により算出
(大阪地裁平成7年12月11日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>将来改善の見込みがなく,日常生活全般にわたり付添介護を要する被害者の将来の介護費用として日額4500円で平均余命まで新ホフマン係数で中間利息を控除して認定した事例
担当医師の指示に基づき母親が付き添って看護した573日につき日額4500円で認定
被害者の後遺障害の内容,程度,日常生活状況によれば,被害者の後遺障害が将来改善する見込みはなく,日常生活全般について付添介護を要すると解される。
日額4500円で平均余命まで新ホフマン係数で認定
(大分地裁平成7年11月14日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>介助なしには日常の基礎的動作をなすことが不可能になった被害者が医師の指示で入居した完全看護の老人ホームにつき,その介護料(入居料)の7割を事故による損害と認めた事例
被害者が事故前は心身ともに健康であったこと,事故による重篤な症状のため自宅での介護は到底困難な状態にあったと認められることに照らすと,Bへの入居による支出のうち,食費などの経費を控除した7割の額を,必要な治療費ないし介護料として本件事故による損害と認めることが相当である。
(東京高裁平成7年2月28日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>1級の後遺障害を残す被害者の将来の介護費として,被害者の状態に鑑み1日当たり4500円を平均余命である56年にわたり認めた事例
被害者は両下肢完全麻痺,暴行直腸障害等があり,排尿,排便,入浴等について独力でなすことができないが,入院中の状態からすると,自宅を改造すればある程度自分で出来るようになると推認できること,被害者は車椅子の操作ができ,他人に運転席に乗せてもらえれば自動車を自ら運転可能な程度に自立した状態にあることにより,同人には介護の必要性はあるものの,四六時中付きっきりでの介護を必要とするものとはいい難く,その費用は1日4500円をもって相当と認め,症状固定日における平均余命56年間分を将来介護費として認める。
(東京地裁平成6年11月17日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>介護用物件につき使用頻度,耐用年数等を考慮して損害額を決め,合わせて介護をする母親の健康面を考慮して将来の介護費を決めた事例
被害者を介護出来るのは母親だけであるところ,その母親もくも膜下出血を発症し,2度の手術を経て頭痛,ふらつきなどの後遺症を残している。このような事実のもとで母親が精神的肉体的に負担の重い介護をいつまで継続出来るか予断を許さない状態である。そこで,母親50歳時までの6年間は日額5000円,その後被害者の平均余命に至るまでの49年間は日額1万1560円(職業付添人の費用)の付添介護費を認めるのが相当である。
(大阪地裁平成6年9月29日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>1級の後遺障害を残す被害者の将来の付添看護費として,1日当たり2500円を平均余命である52年にわたり認めた事例
被害者は退院後,自宅での生活に際し,家族による付添看護が必要であり,その1日当たりの費用は2500円と認めるのが相当である。
被害者の平均余命は少なくても52年あるので将来の付添看護費の本件事故当時の現価は次のとおりである。
2500円×365×(25.5353-0.9523)=2243万1987円
(大阪地裁平成6年9月13日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>併合1級の少年の将来の介護料につき,母親の仕事,年齢を考慮して一定期間につき近親者介護料に代えて職業付添人の介護料を認めた事例
養護学校卒業後自宅療養となる平成7年4月からは,中学校教員のは保谷が60歳の定年に達するまでは年間で平日の240日間は職業的介護人(1日1万6800円の介護料)による介護料を,125日の休日については近親者(1日4500円の介護料)による介護料
母親定年後から70歳に達する翌春までの10年間は近親者(1日4500円の介護料)による介護料
それ以降被害者が平均余命に達するまでは母親が高齢であるため近親者による介護は無理であり職業介護人(1日1万6800円の介護料)による介護料
(東京高裁平成5年5月26日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>退院後の付添看護費用(1日5000円)を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
被害者の母親は,被害者が入院中鬱状態になったこともあって精神科担当医師の指示に基づき合計331日にわたって被害者を外泊させて付き添ったり,また指定された授業参観もしくは面会のために医療機関に赴いて被害者に付き添った。
また,被害者の両親は,退院後1663日間について被害者を常時介護していた。
本件損害としての付添費は,1日当たり5000円と認めるのが相当である。
(神戸地裁平成5年4月30日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。
<弁護士・交通事故裁判例>後遺障害1級の被害者の将来の看護費につき81歳まで1日4500円の割合によるとし,入園中の養護ホームの費用を基準にしないとした事例
被害者の後遺障害の内容,程度,同人の全日常生活の動作,活動には第三者の全介助を必要とすること,同人は症状固定時に66歳でその平均余命は15.21年であることより,将来の看護費として被害者の81歳まで1日当たり4500円の割合で認めるのが相当である。
被害者は病院を退院後特別養護老人ホームに入園して現在に至っているが,被害者の現在の介護は老福法に基づく福祉措置で,そこで要する費用は,市により決定されるものであり(老福法28条1項)私法である損害賠償法とは別個の法関係であるし,そこにおける徴収金の金額自体も一定しておらず,被害者の同老人ホームにおける入園生活も前記看護期間中継続されるという完全な保証もない。しからば被害者の同老人ホームにおける費用をもって将来の看護費算定の基礎金額とするのは相当でない。
以上より,被害者の将来の看護費の現価額をホフマン式計算法で算定すると(4500円×365)×10.584=1738万4220円(過失相殺前)である。
(神戸地裁平成5年4月28日判決)
交通事故、借金、離婚、相続、刑事事件、労働問題、企業法務など、佐賀県全域から幅広いご相談をお受けしています。
示談や慰謝料、過払い金返還なども、まずはお気軽にご相談ください。
企業の顧問契約も承ります。
一人ひとりのご依頼者様にとっての「身近な専門家」として、何でも気軽にご相談いただける弁護士を目指します。
信頼いただけるよう力を尽くします。